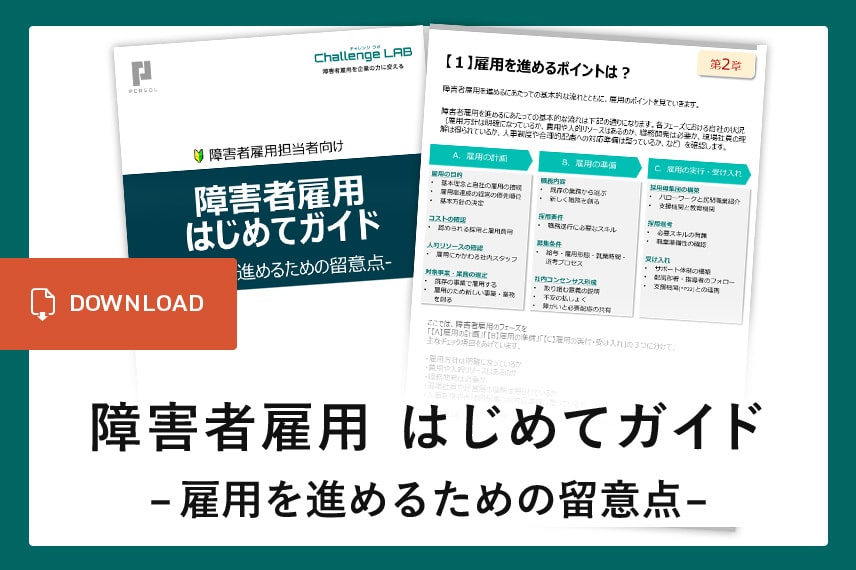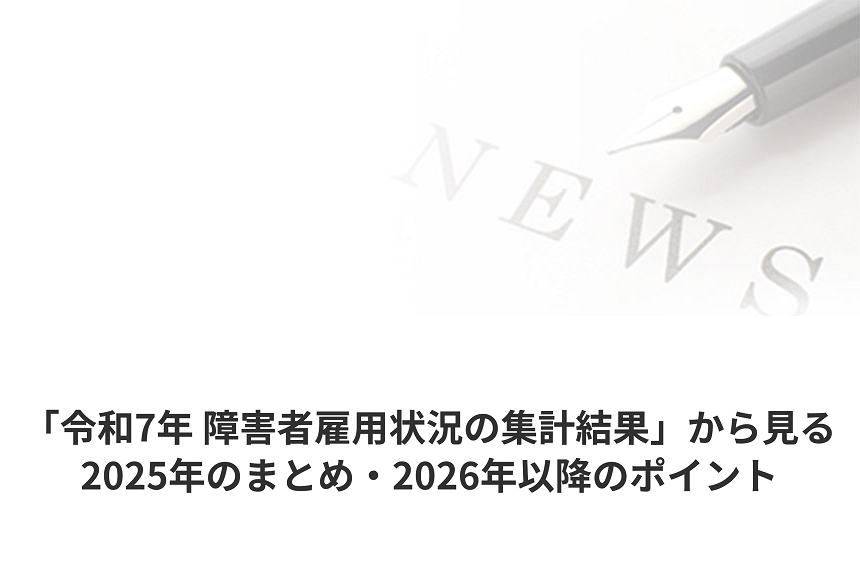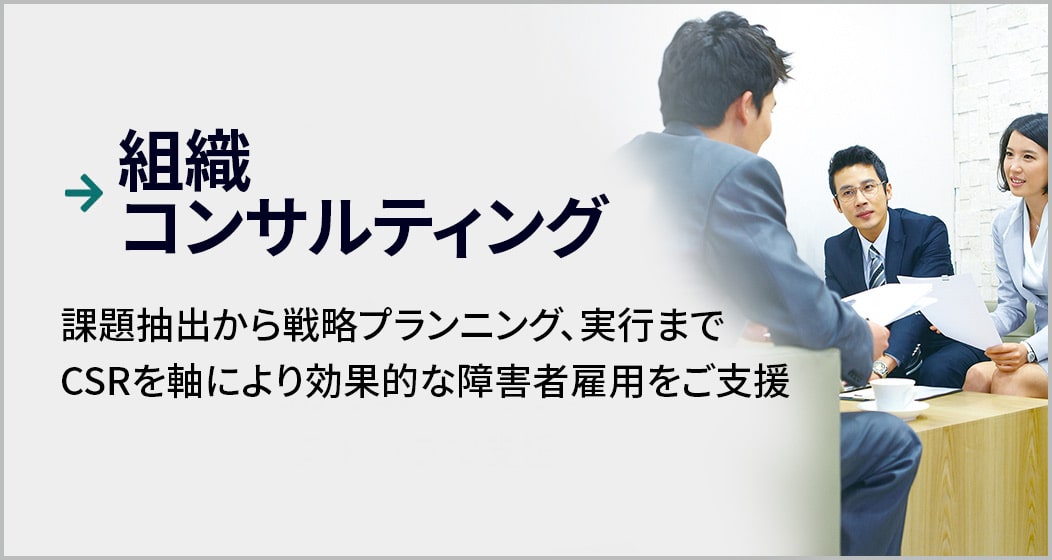社会の変化や障害者雇用政策によって、民間企業による雇用数は年々増加しています。しかし、最新の集計によると、法的義務である雇用率達成企業は半分以下にとどまっているほか、雇用現場では様々な問題や弊害が生じています。そこで今回は、経済学の視点から、障害者雇用政策を「社会全体の生産性向上を実現するための政策」ととらえ、現在の政策の問題点や企業の課題、あるべき「障害者の経済参加モデル」と、企業の果たす役割について、慶応義塾大学の中島隆信教授にお話を伺います。

慶応義塾大学商学部教授
中島 隆信
1960年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒。同大学大学院経済学研究科後期博士課程単位取得退学。博士(商学)。2001年より慶応義塾大学商学部教授。経済学をさまざまな分野に応用し、新たな視点を提示する多くの著作を発表している。著書に、『新版 障害者の経済学』『高校野球の経済学』『大相撲の経済学』(以上、東洋経済新報社)、『経済学ではこう考える』(慶應義塾大学出版会)など。
- 目次
-
社会政策としてみた現在の障害者雇用政策
法定雇用率の果たした役割

今の日本の障害者政策の柱ともいえる「法定雇用率」は、ご存知のように「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)によって企業に一定の雇用率達成を義務化するものです。本来の障害者の社会参加のあり方について考えると、もちろん、自発的に障害者を雇用するのが一番望ましいのですが、企業によっては、障害者について認識・知識不足であるほど雇用に消極的となり「とりあえず納付金で」という対応にもなるでしょう。
その一方、実際に雇用してみたら予想以上にはたらけることを知り、現場も慣れてきて「こういう工夫をすれば、障害のある人たちもうまく就労できる」というふうに知恵やノウハウを蓄積する企業もかなり増えてきたはずです。
総じて振り返ると、障害者の雇用義務化は、雇用政策のファーストステップとしては決して間違ってはいなかったと思います。一定の役割も果たした、と私は評価しています。さまざまな業種で数多くの企業が障害者雇用に取組むきっかけになったのは大きな成果です。
現在の労働力人口における障害者数を考慮すると、法定雇用率は今後も上がり続けるでしょう。その流れのなかで、従来の障害者雇用の進め方がどこまで通用するのかという点については疑問があります。現在の障害者政策や制度そのものと、企業が目指すべき方向性について、改めて見直す時期に来ているのではないかと思われます。
配慮か差別か
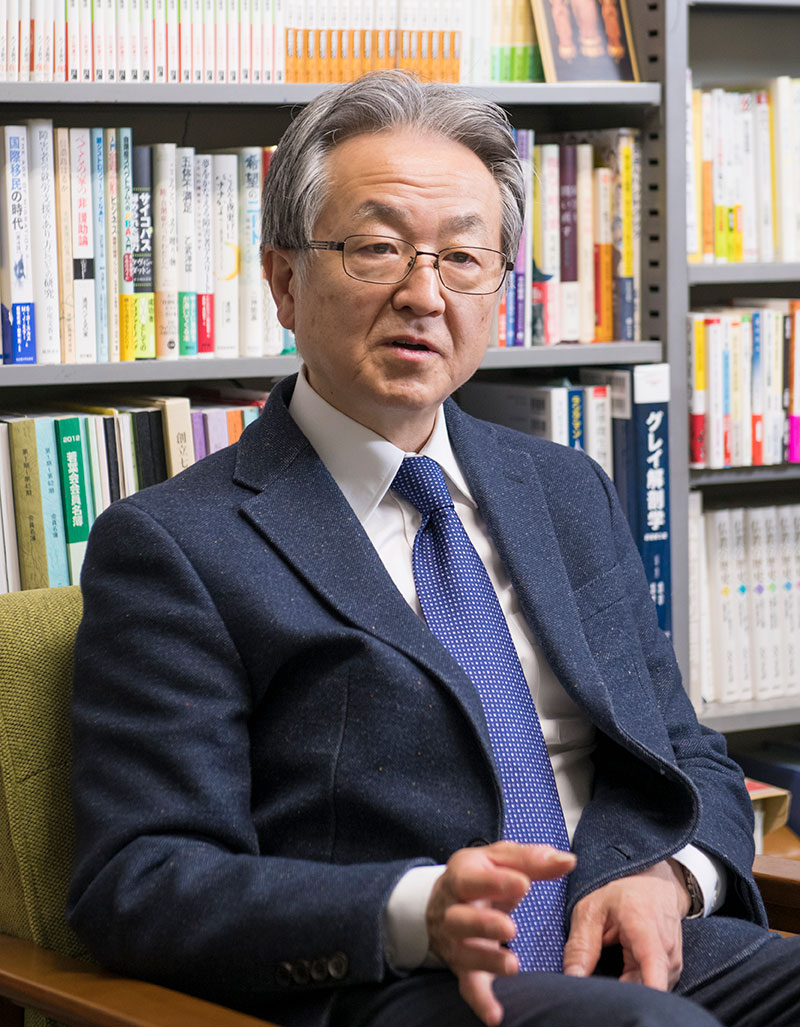
障害者雇用率の義務化が始まった1976年は、対象が身体障害者だけでした(雇用率1.5%)。就労の課題はおもにハード面でしたから、企業もある程度のリフォームや、デスクワーク中心の業務などを割り当てるなどの工夫ができました。その後、法定雇用率の算定基礎の対象に知的障害者が加わると(97年)、とくに大企業では一般の職場への配属に無理があるとして、特例子会社をはじめとする特別な職場をつくるなどして雇用を拡大してきたと思います。2018年に精神障害者が加わると、これまでとは違った配慮が求められるケースも増えてきました。
障害者が一カ所に集まり決まった軽作業をするような労働形態は、確かに配慮の一つです。その一方、障害者という枠だけで集められるのは差別ではないかという意見もあります。そして2016年に改正施行された障害者雇用促進法では、雇用において障害者に対する差別は禁止され、「合理的な配慮」の提供が義務となりました。
配慮と差別は、いわば表裏です。配慮と考えるか差別と考えるかは、環境が決めます。現在のようにはたらき方が多様化しつつある社会において、決められたはたらき方だけを押しつけられるのは配慮というよりも、むしろ差別に近いかもしれません。今後さまざまな機器やソフト技術の発達によって障害者の職域もさらに広がるはずですし、自分の得意な能力を伸ばしたいという人も増えていくでしょう。社会全体において、硬直化した労働形態がふさわしくない時代になりつつある中で、障害者一人ひとりも、自分のはたらき場所やはたらき方を選べるということが重要視されてきています。
雇用における配慮とは

障害者雇用における配慮について、少し視点を広げてみましょう。私たちは一人ひとり「できることとできないこと」があり、社会のなかで、できることをうまく仕事に結びつける工夫をしています。こうした工夫を「配慮」と言い換えるなら、新人社員にも最初は簡単な仕事から教え、徐々に慣れてもらうという配慮があります。
障害者雇用の場合も同じように「一人ひとりの能力を見極めながら仕事に結びつけるための配慮」を考える必要があります。
例えば知的障害の場合、論理的思考や計算能力で困難な部分が出てくることもありますが、そうした能力を必要としない仕事はいくつでもありますし、周囲の人が柔軟に補助しながら業務を進めることもできます。精神障害の場合は、調子のいいときは普通にはたらけても崩れると「全然ムリ」といった具合に波が生じることもありますから、そのときには労務管理において工夫が必要です。発達障害の方は自閉傾向から注意欠陥多動、学習障害などさまざまな特性があるので、抜きん出た能力を仕事に結びつけることも配慮と言えるでしょう。
社会全体の生産性向上実現のための、障害者の経済参加のあり方
企業だけがコスト負担?

ところで、障害者雇用における配慮については、企業の経営が成り立つこともセットにして考えていかなければなりません。そこで問題になるのは、配慮のためのコストを誰が負担するかです。すべて企業だけに押しつけてしまうと、障害者雇用はうまくいきません。カギとなるのは、社会全体としていかに就労と福祉を連携させていけるかです。
分かりやすい例を紹介します。少し前に、重度障害者の方が参議院議員に当選しましたが、いざ活動しようとすると、従来の法律制度では「議員活動中の公費による介護サービス」を受けられないことが分かりました。雇用された途端に当事者は福祉サービスの対象外となり、付随する負担がすべて雇用主に移ってしまうからです。今回のケースでは急きょ所属する参院が費用を負担し、制度の見直しも始まりました。
これは日本の障害者政策において、雇用と福祉の制度・運営が非効率なタテ割り式となっているために起こった問題です。一般社会でも同じように、就労と福祉サービスの断絶に苦労されている方が数多くいらっしゃるはずです。
どんな制度をつくり、どんな形で誰がコストを負担すれば一番うまくいくかを考えるのが制度設計ですが、これは行政の責任です。配慮コストの判断基準は、その人がはたらくために必要なコストと、その人がはたらいた結果生み出される価値を天秤にかけ、どちらが大きいかによります。価値が大きければ、コストをかけるほうが社会全体にとってメリットになります。その人がはたらくことを諦めてしまったら、生活保護といったさまざまなセーフティネットにかける社会全体のコスト負担が増えるからです。基本は、はたらく能力があるならはたらいたほうがいいのです。
ただし企業のコスト負担だけを基準にすると、雇用するか否かのハードルは高くなります。社会の配慮が整っていれば、企業も極端な負担を強いられることもなくなり、結果的にその人が企業の生産性に貢献することにも結びつきやすくなる。これが障害者の経済参加のあり方だと考えます。
外部委託・みなし雇用
障害者の経済参加の形態として、いくつかの企業がA型やB型事業所に業務を委託することで雇用を創出する「みなし雇用」も検討すべきだと私は思っています。

企業が全責任で雇用すべき」とする行政側は「業務委託の分を雇用率にカウントするなんてありえない」と言うでしょう。私も100%雇用率にカウントすることについては賛成しません。雇用率の範ちゅうではなく、別の指標とするのも手です。直接雇用〇%、みなし雇用〇%の結果として「弊社は障害者〇人分の仕事をつくっています」という公表の仕方をすればいいのです。こうした外部委託式は、スウェーデンの国営企業サムハルが有名です。
すでに三重県でも取組みが始まっています。ミルボンというシャンプーや化粧品をつくっている企業の工場があるのですが、一部の業務をB型事業所に発注しています。三重県では、その分の雇用の創出も算出しています。雇用ではなく、何人分の仕事を出しているという発表の仕方ですね。このみなし雇用は、近年見かけるようになったいわゆる「雇用の肩代わりビジネス」、施設で障害者に野菜をつくらせ、それを売らずに、お金を出した企業が社員に配布するような“虚業”とは違います。
外部委託による雇用創出を、三重県では「インクルーシブ雇用」と呼んでいます。B型事業所の月あたり平均工賃1万数千円が、企業からの委託業務によって6万円ぐらいに増えると、障害者の生活も劇的に変わります。本人の人生がどれだけ変わるかという視点も見落とすべきではありません。

企業や組織側の視点だけで雇用を考えていると、トータルで社会にどんな変化が起きるかというような評価が伴ってきません。日本の行政側も、B型事業所に工賃を上げろ、A型事業所には施設を増やせ、企業にも雇用率を上げろと言っていますが、全体として考えると矛盾しています。これは「タテ割り行政」の典型的な悪い点です。本来なら企業に就職できるような人が、B型で少しの給料しかもらえないのは問題です。その人の工賃を上げるよりも、その人を一般の企業に就職させてあげればいい。企業ではたらくのが難しいならA型ではたらき、企業はそこに仕事を発注すればいい。結果として本人が望む、本人にとって望ましいはたらき方ができることが重要であるはずです。タテ割りではなく「全体最適」を図るための制度設計が大切なのです。
企業ができること
グループ適用を外す
行政の政策や制度上の課題は簡単には変えられませんが、各企業の取組みは経営トップ次第でいかようにもなります。これからの障害者雇用について、企業が目指す方向性を考えてみます。
まず私は最近、企業の方によく「子会社のグループ適用を外したらどうか」と言っています。この制度の意義は認めていますが、「企業としてはグループ適用をしない」という方向でいくべきだと考えています。グループ適用によって、特例子会社など決まった現場に雇用義務を押しつけ続けることは、これまで述べてきたように、さまざまな面で限界にきています。

今後は、法定雇用率が上がっていくにつれ、特例子会社の仕事をこれ以上増やせないため、グループ適用をやめざるを得なくなる企業も出てくるかもしれません。特に大手企業では、初期に雇用された身体障害者の方たちが軒並み定年を迎えていることも転機となるでしょう。
実際にグループ適用をしていない大企業もあります。子会社の現場業務で、それぞれ障害者の仕事をつくるのです。子会社はいわば中小企業のようなものですから、発想を変えることで障害者雇用を進めやすくなるかもしれません。
ただし最初から現場にすべて押しつけるのではなく、特例子会社など障害者雇用の現場で経験を積んだ人が各現場を回って知恵を伝授するといいでしょう。退職した方も活用すべきです。これは配慮のコストを下げる重要な工夫です。こうした環境を整えるための方針を出すのは経営陣の役目ですね。

子会社がそれぞれ障害者を雇用していくとなった場合には、通勤の課題も出てきます。特に公共交通機関が十分ではない地方にいくと、障害者の通勤は予想以上に困難です。企業の雇用は「自力で通勤できる人」が前提でしょうから、そこにどれだけ福祉サービスを絡めていけるか。地域の就労支援機関などと連携しながら解決できれば、地方の雇用もかなり進むと思います。
企業内のグループ適用をやめると、どうしても雇用率を達成できない子会社も出てくるかもしれません。その場合は、子会社から親会社に納付金を払ってもらいます。例えば1人不足分で月20万円とし、ほかの障害者雇用をしている子会社などに仕事を発注した分は免除するといった具合です。「企業版みなし雇用」というわけですね。
現場をプロフィットセンターに
もちろん特例子会社といった形態も、変わらず一定の役割があります。企業の規模や業種によっては、本人がはたらきやすく戦力化しやすいというメリットが確かにあります。その場合に企業が考えるべきは、いかに現場のモチベーションを上げていくか、いかに本業として利益につなげていけるかです。

障害者のなかにも、本当に単純作業が好きで得意な人もいれば、そうじゃない人もいるし、もっと複雑な、コミュニケーションを要する仕事もできる、やりたい人もいますよね。清掃作業も、単純なものから複雑なものまでスキルアップしていけます。社内のトイレだけでなく、事業として、ホテルや外部施設に営業して業務として請け負っていけるようになれば立派な本業になります。
そのようにして障害者雇用の現場を、コストセンター(利益を生み出さない部門)ではなくてプロフィットセンター(利益を生み出す部門)的な場所にするようなビジネスモデルを考えていきます。実際に実現している企業も増えてきています。
たとえば接客業では、牛丼チェーン店を展開する大手企業が、障害者を店舗に出しています。ただしローカルの郊外店に限っています。都心部はお客さんが殺気立っていて難しいのだそうです。今後はICTの活用によって、障害者が現場に出ていけるハードルも下がっていくでしょう。最近は居酒屋なんかでもタッチパネル式の注文ができますから、その場でメニューを覚える必要がなくなりました。それでも困ったときはとりあえず「しばらくお待ちください」という台詞だけ言えればいいと思います。私がスウェーデンで訪れたファストフード店でも、タッチパネル式を採用して障害者が十分にはたらけている様子を見ました。
障害者を現場に出していく上で欠かせないのは、職場や社会の寛容さなのだと思います。企業においては、やはり社員教育が大切だということは言わずもがなです。
働き方改革として
長期的な視野に立ち障害者雇用を進めていく上で、柱とすべき考え方を改めて挙げておきたいと思います。

最も大事なことは「障害者を本業での戦力とする」ということです。障害を持つ従業員の戦力化には「多様なはたらき方」を提示していく必要があります。「はたらく上で何が障害か」を考える視点は、どんな従業員にもあてはまります。例えば出産・育児にかかわったり、家族の介護が必要になったりした従業員には、それぞれ一定期間の支援が必要になります。そういう人たちにもテレワークといった多様なはたらき方が提示できなければ戦力にできませんよね。
「はたらき方を人間に合わせる」という姿勢も重要です。実は、障害者への配慮から学べることがたくさんあります。例えば、ユニバーサルデザインに代表されるように、障害者の困りごとを解消する工夫が誰にとっても便利なことが数多くあります。また、自分の得意なことをいかしてはたらきたいのは誰でも同じですが、知的・発達障害を持つ人の場合は、それがないと雇用に結びつかないという点で優先度が高くなります。精神障害の場合は「ワークライフバランス」。適度に休まないといけないのは私たちも一緒です。
こうしたさまざまな職場改善が、本来の働き方改革だと私は考えます。障害者雇用にともなう配慮や工夫に向けた努力によって、従業員一人ひとりが能力を発揮し幸福度も高めていければ、おのずから企業全体の生産性向上と成長へとつながっていくはずです。
※所属・役職は取材当時のものです