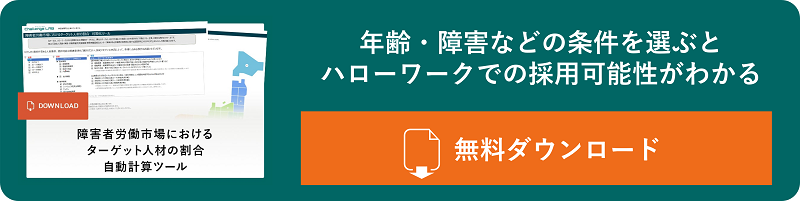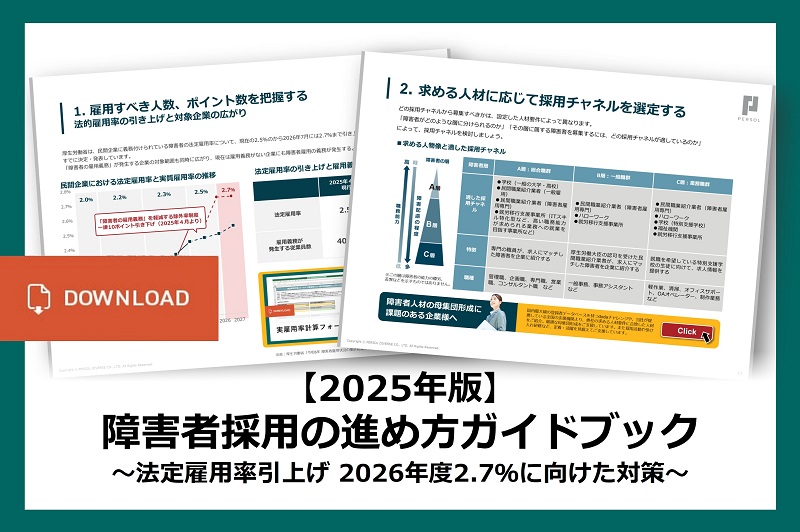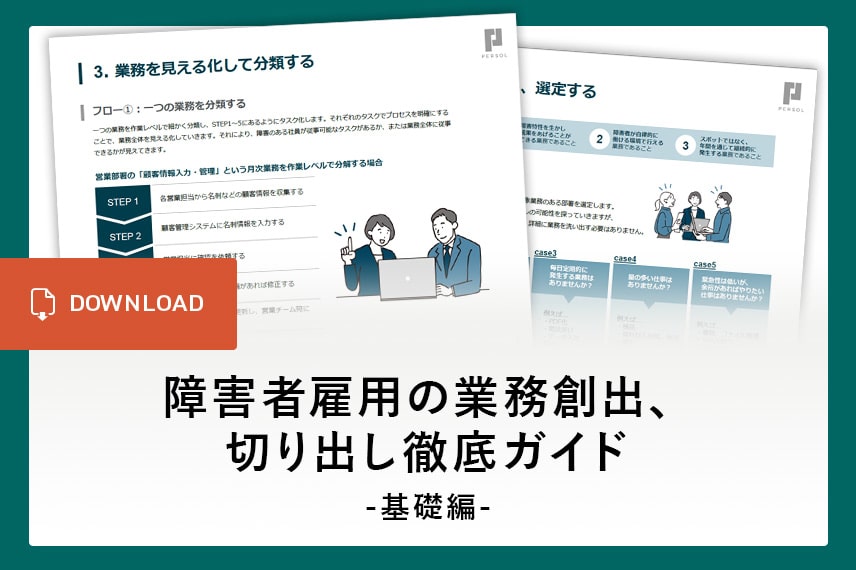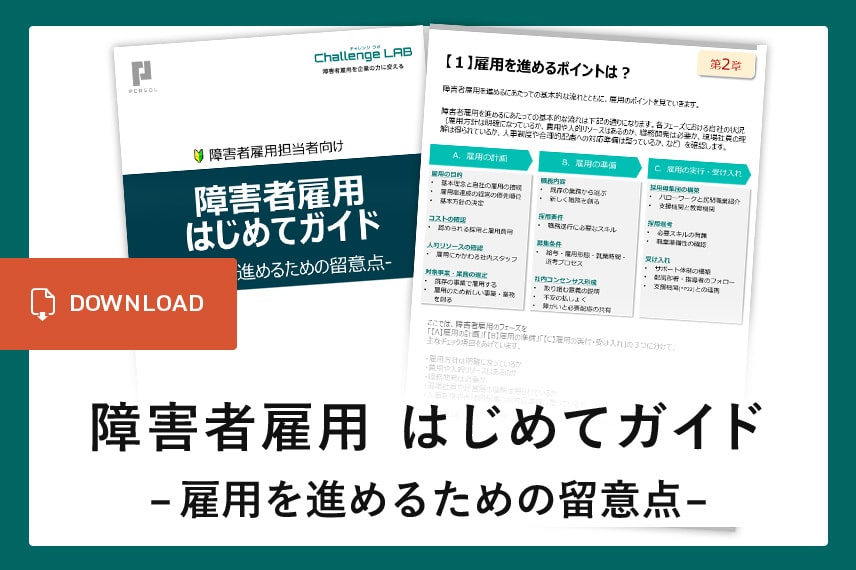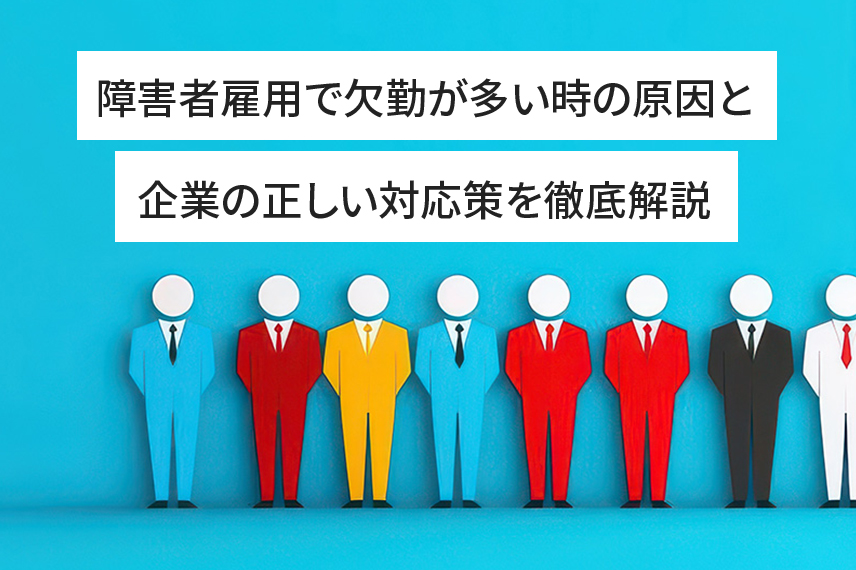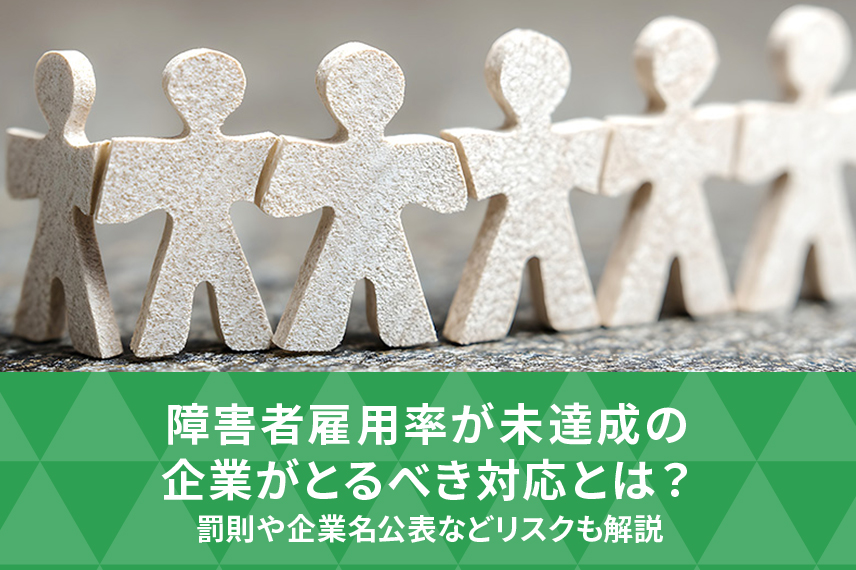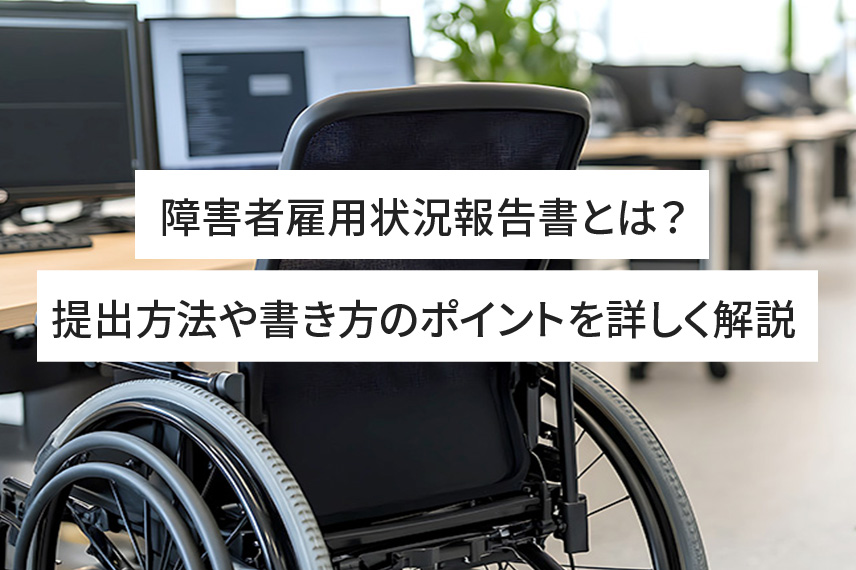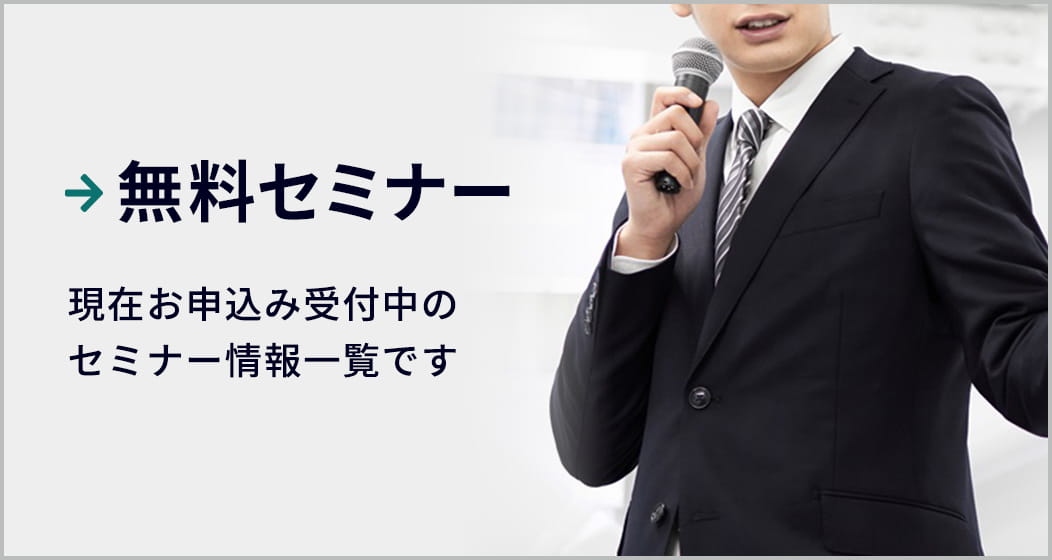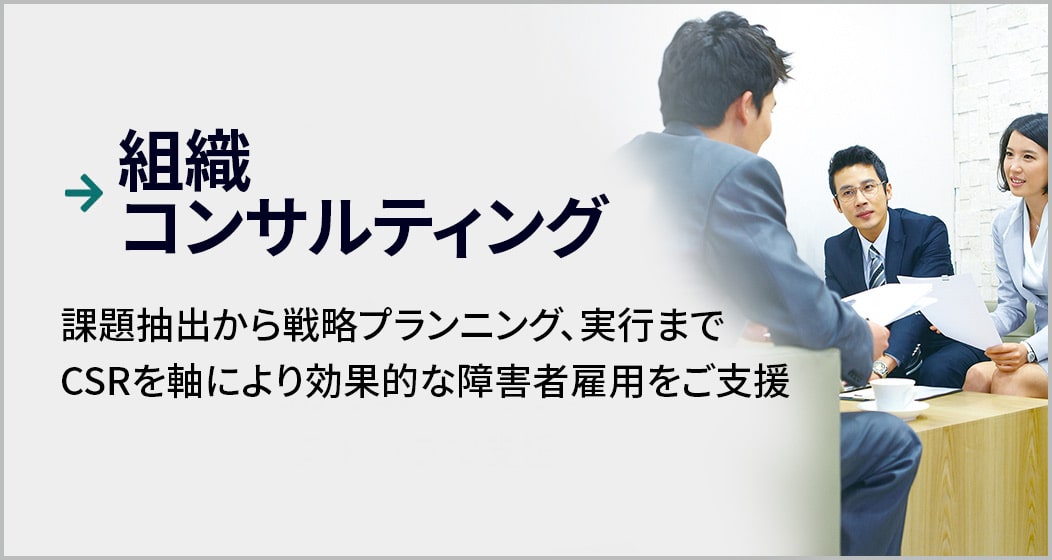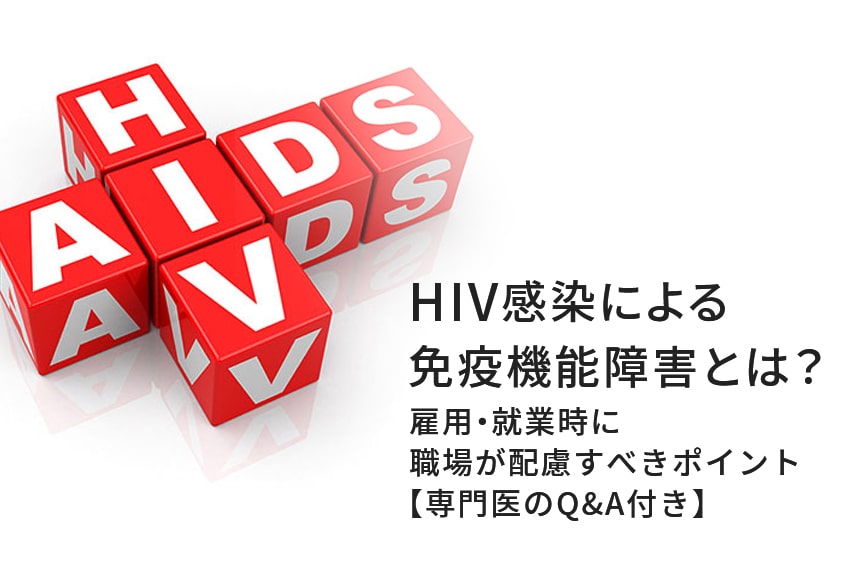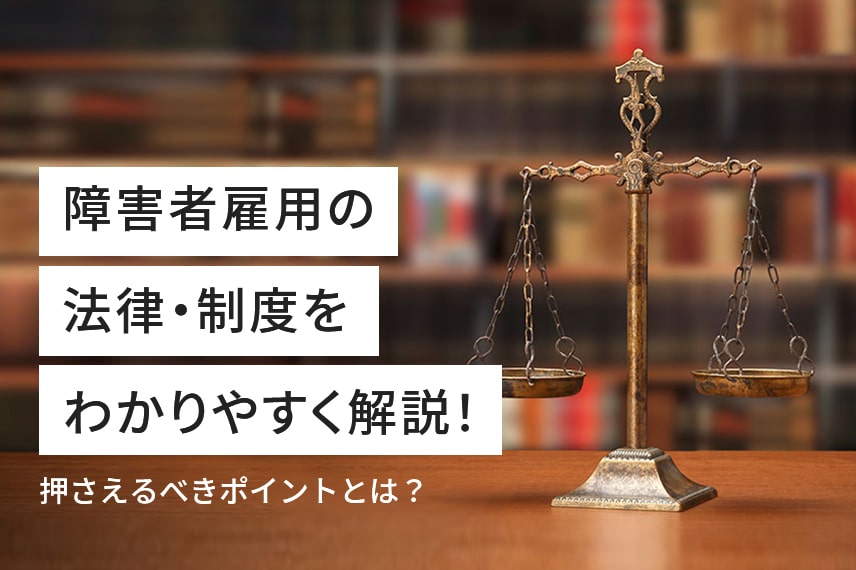作成日:2025年11月25日
障害者雇用を進める上で求職者とのマッチングが不安な企業もあるでしょう。特に障害者雇用の経験が浅い企業では「長く働いてくれるだろうか?」「職場の雰囲気に合うだろうか?」「自社で適切にサポートできるのだろうか?」など不安を感じやすいものです。
そんな企業におすすめなのが「障害者トライアル雇用」です。障害者トライアル雇用では、トライアル期間に実際に職場で働いてもらうことで、職場や職務へのマッチングを確認できます。
本記事では、障害者トライアル雇用の制度内容や利用できる助成金、導入の流れから成功のポイントまで詳しく解説します。
- 目次
-
障害者トライアル雇用制度とは
障害者トライアル雇用制度は、原則3ヶ月間の試行雇用を通じて、適正や能力を見極め、継続雇用のきっかけを作ることを目的とした制度です。ここでは、障害者トライアル雇用制度の対象や期間、活用実績について解説します
障害者トライアル雇用の対象者
障害者トライアル雇用は、「障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条第1号」に定める障害者に該当する方のうち、下記のいずれかの要件を満たす人が対象になります。
- 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している
- 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
- 紹介日の前日時点で、離職している期間が6か月を超えている
※重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の方は上記1~3の要件を満たさなくても対象となります。
障害の原因や障害の種類による条件はありません。
障害者トライアル雇用の期間
障害者トライアル雇用の期間は、原則として3ヶ月ですが、精神障害者は原則6〜12ヶ月間のトライアル雇用期間を設けることができます。
障害者トライアル雇用助成金の期間とは異なるので注意が必要
障害者トライアル雇用に関連した助成金については後ほど詳しく解説しますが、障害者トライアル雇用の期間と障害者トライアル雇用助成金の期間は異なるため、注意が必要です。
障害者トライアル雇用の活用実績
障害者トライアル雇用は継続雇用のきっかけを作ることが目的ですが、実際にどれくらいの実績があるか気になる方も多いでしょう。厚生労働省は、障害者トライアル雇用の継続率を発表しており、令和2年〜令和4年のデータは以下の通りになっています。
- 令和2年:(2020年):81.4%
- 令和3年:(2021年):80.4%
- 令和4年:(2022年):80.3%
トライアル雇用終了後も8割以上の方が継続して雇用されていることが分かります。
障害者トライアル雇用で利用できる助成金とは?

障害者トライアル雇用を推進するために、障害者トライアル雇用を利用した企業を対象にした助成金制度があります。障害者トライアル雇用助成金の受給額や受給条件、申請のタイミングや申請書類について解説します。
受給額
受給額や支給期間は精神障害者か精神障害者以外で異なります。対象者1人当たりの受給額と支給期間は下記の通りです。
| 対象者 | 支給額 | 支給期間 |
|---|---|---|
| 精神障害者以外 | 月額最大4万円 | 最長3ヶ月間 |
| 精神障害者 | 最初の3ヶ月:最大8万円 4ヶ月目以降:月額最大4万円 |
最長6ヶ月間 |
精神障害者以外の場合は、支給期間はトライアル雇用の期間と同じく3ヶ月となります。一方、精神障害者のトライアル雇用の期間は6〜12ヶ月ありますが、支給期間は最長6ヶ月間となるため留意しておきましょう。
受給条件
トライアル雇用助成金を受け取るためには、対象者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介によって雇い入れることが条件となります。また、雇用保険被保険者資格の取得の届出を行うことも必要です。
さらに、雇用関係助成金共通の要件など他にも満たすべき条件があるため、申請する前に条件に当てはまっているか確認しておきましょう。雇用関係助成金共通の要件は下記の通りです。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
- 支給のための審査に協力すること
- (1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
- (2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
- (3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
- 申請期間内に申請を行うこと
申請に必要な書類
障害者トライアル雇用助成金に必要な書類は、「実施計画書」と「支給申請書」の2種類です。
実施計画書は、トライアル雇用開始日から2週間以内に対象者を紹介したハローワークに提出する必要があります。実施計画書を提出する際は、雇用契約書など対象者の労働条件が分かる書類を添付してください。
支給申請書は、トライアル雇用が終了した後に提出する資料です。トライアル雇用終了日の翌日から2ヶ月以内に事業所を管轄するハローワークまたは労働局に提出してください。
申請先と提出期限
障害者トライアル雇用助成金の各書類の申請先と提出期限は以下の通りです。
| 書類の種類 | 提出先 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 実施計画書 | 対象者を紹介したハローワーク | 開始から2週間以内 |
| 支給申請書 | 事業所を管轄するハローワークまたは労働局 | 終了日の翌日から2ヶ月以内 |
障害者トライアル雇用を延長した場合や障害者トライアル雇用の途中で継続雇用へ移行した場合などは、支給申請期間が異なる場合があるため、ハローワークに問い合わせましょう。
障害者トライアル雇用と障害者短時間トライアル雇用との違い
障害者トライアル雇用には、短時間であれば働ける方を対象にした「障害者短時間トライアル雇用」制度もあります。障害者短時間トライアル雇用は、精神障害者または発達障害者で、週20時間以上の就業時間での勤務が難しい人が対象となります。
まずは、週10時間以上20時間未満の短時間の試行雇用から開始し、職場への適応状況や体調などに応じて3ヶ月から12ヶ月間のトライアル期間中に20時間以上の就労ができることを目指します。
また、助成金についても、「障害者短時間トライアル雇用」に対応した「障害者短時間トライアルコース」が存在します。ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れた対象者1人につき、月額最大4万円を最大12ヶ月受給することができます。
障害者トライアル雇用の仕組みと流れ

障害者トライアル雇用の仕組みと流れは下記の通りです。
- 求人申し込み
企業が「障害者トライアル雇用求人」をハローワーク等に提出する - 求職登録・職業相談
求職者がハローワーク等で求職登録・職業相談を行う - 職業紹介
対象者の確認や各種支援を行ったのちに、対象者に企業を紹介する - 選考面接
企業は対象者の選考面接を行う - 障害者トライアル雇用開始
企業が対象者の障害者トライアル雇用を開始する - 実施計画書の作成・提出
開始から2週間以内にハローワークに実施計画書を提出する - 障害者トライアル雇用終了
継続雇用に移行するか、雇用期間満了するか決定する
助成金を希望する場合は、トライアル雇用終了日の翌日から2ヶ月以内に事業所を管轄するハローワークまたは労働局に支給申請書を提出する必要があります。
障害者トライアル雇用のメリット・デメリット
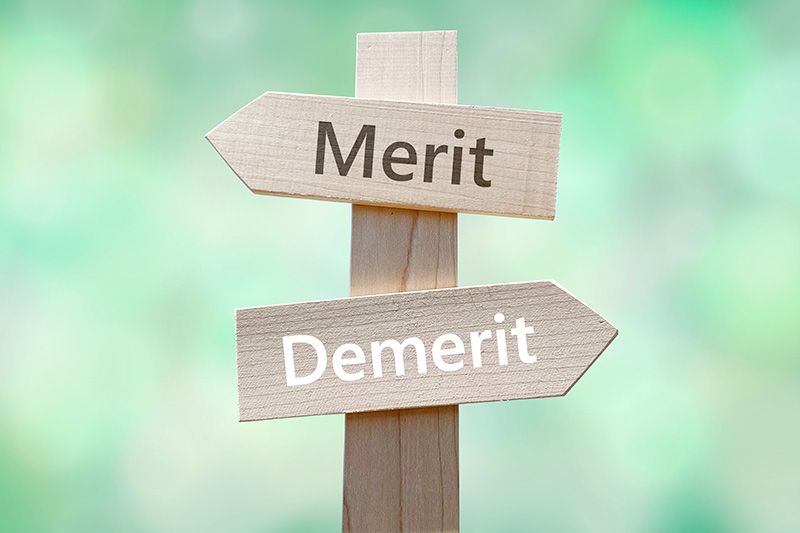
障害者トライアル雇用は多くのメリットがある一方で、注意したいデメリットもあります。ここからは、障害者トライアル雇用のメリット・デメリットについて解説します。
障害者トライアル雇用のメリット
まずは障害者トライアル雇用のメリットについて紹介します。障害者トライアル雇用の主なメリットは下記の通りです。
- 助成金活用により、採用コストを削減できる可能性がある
- 定着率に期待がもてる
- 採用競合による求職者の重複応募
それぞれ詳しく紹介します。
助成金活用により、採用コストを削減できる可能性がある
トライアル雇用では、トライアル雇用助成金を利用することができるため、採用コストを削減できる可能性があります。
精神障害者以外の場合は一人当たり最大12万円、精神障害者の場合は一人当たり最大36万円の助成金を受給できます。特に中小企業など採用に費用をかけるのが難しい企業にとっては、採用コストを削減できることで、障害者雇用の促進につながるでしょう。
定着率に期待がもてる
精神障害者以外は3ヶ月、精神障害者の場合は6〜12ヶ月の間、実際に職場で働いてもらうことで、ミスマッチを減らすことができ、定着率の向上が期待できます。
企業側が求職者の適正や能力を測ることができるだけでなく、求職者側も職場の雰囲気や業務内容があっているか確認できます。
特に障害がある場合は、障害にあわせた配慮が必要となりますが、うまくサポートできるか・サポートしてもらえるかは企業にとっても求職者にとっても不安なものです。せっかく採用しても早期離職となれば、採用にかけたコストが無駄になってしまいます。
障害者トライアル雇用を利用することで、企業・求職者の両者がお互いに理解を深めることで、トライアル雇用終了後の定着率にも期待がもてるでしょう。
採用競合による求職者の競争を避けることが可能
求職者が障害者トライアル雇用に応募する場合、基本的に同時に複数の企業に応募することはできません。そのため、採用競合による求職者の競争が発生しにくく、企業側としては選考がスムーズに進みやすい状況となります。
通常の採用活動では、求職者が複数の企業に同時応募しているケースが多く、優秀な人材に内定を出したとしても、他社の選考状況によって内定辞退や選考辞退が発生する可能性があります。
一方、障害者トライアル雇用では求職者が応募先を慎重に選び、単一の企業に応募するケースが中心となるため、採用競合が少なく、企業側としては採用につながりやすいといえるでしょう。
障害者トライアル雇用のデメリット
障害者トライアル雇用の主なデメリットは下記の通りです。
- 面接対応における工数が増加する可能性がある
- 「トライアル雇用専用求人」として求人票を出す必要がある
- 応募が減少する可能性がある
障害者トライアル雇用を利用する上で、メリットだけでなく、デメリットもしっかり理解しておきましょう。
面接対応の工数が増加する可能性がある
障害者トライアル雇用制度では、選考は書類ではなく面接で行う必要性があるため、面接対応の工数が採用業務の負担になることがあります。
面接を行うことで書類だけでは分からない障害特性や人柄が分かることは企業にとってメリットです。しかし、想定以上に応募者が多かった際などは、面接対応の工数が増える可能性があります。面接対応の工数が増加する可能性についても留意した上で計画を立てるようにしましょう。
「トライアル雇用専用求人」として求人票を出す必要がある
障害者トライアル雇用を行う際は、募集時の求人票より「トライアル雇用専用求人」として求人票を出す必要性があります。そのため、選考を進める過程で、企業都合にてトライアル雇用を打診することはできません。実施計画書の作成や入念な採用計画・しっかりした受け入れ態勢を前提にした制度である点は事前に理解しておきましょう。
応募が減少する可能性がある
障害者トライアル雇用制度を利用することで、応募が減少する可能性があります。
トライアル雇用期間があるため、契約社員・正社員スタートの障害者求人に比べると心理的ハードルが低く、社会人経験の浅い求職者も応募しやすかったり、未経験職種にも挑戦しやすかったりする点は求職者にとってメリットです。
しかし、お試しでの雇用と捉えられる可能性もあり、「正社員求人・契約社員求人」と比べると見劣りすると考え、応募を避ける求職者も一定数発生すると考えられます。
障害者トライアル雇用制度のメリット・デメリットを十分に踏まえた上で、自社で取り入れるべきか検討することが重要です。
障害者トライアル雇用の注意点

障害者トライアル雇用を利用する上での注意点を解説します。
求人数を超えたトライアル雇用はできない
障害者トライアル雇用制度では、求人票を作成する時点で設定した求人数を超える人数を雇用することはできません。例えば、求人数1人の求人に多くの応募があり、トライアル雇用したい人が複数いても1人を選ばなければなりません。求人数を超えたトライアル雇用はできないことを踏まえて、求人数を適切に設定することが大切です。
求職者の志向性に偏りが出る可能性がある
障害者トライアル雇用では、求職者の志向性に偏りが出る可能性があります。
トライアル雇用を望まれる方は、共にはたらく同僚や職場環境・職務との適正を見極めたいと考える慎重な方、社会人経験の浅い求職者、未経験職種へのチャレンジしたい方などが比較的多いと考えられます。
「自社にて一から育てたい」「高い定着率に期待したい」といった企業にとってはニーズが合致しますが、そうでない場合は志向性の偏りがミスマッチにつながる場合もあるため、注意が必要です。
障害者トライアル雇用を活用された事業所の事例

障害者トライアル雇用に興味はあるものの、実際に自社でうまく活用できるか不安な方もいるでしょう。障害者トライアル雇用は、さまざまな業界で活用されており、継続的な雇用につながっています。ここでは、厚生労働省が公表している障害者トライアル雇用の事例について紹介します。
畜産食料品製造業での事例
ある畜産食料品製造業の小規模事業所では、障害者雇用の経験やノウハウがなく、障害者雇用に漠然とした不安を感じていました。
そこで障害者トライアル雇用を活用し、養鶏作業員として、重度知的障害・難病の重複障害の方のトライアル雇用を開始しました。「地域障害者職業センター」「障害者就業・生活支援センター」「就労移行支援事業所」が連携し、チーム支援体制で企業と求職者のサポートを行いました。
実際に作業する様子を事前に間近で見たことで、労働能力を確認できたため、障害者雇用への不安を払拭することができました。トライアル雇用終了後は、継続雇用に移行し、障害者就業・生活支援センターが引き続き、企業と雇用された社員の両面の支援を継続しています。
病院での事例
ある病院では、身体障害者を雇用したことはありましたが、精神障害者を雇用した経験がなかったため、トライアル雇用として精神障害者の受け入れを行いました。本人の障害特性を職場内でも共有した上で、休憩時間や通院日など本人の健康を留意した配慮も行いました。
また、どのような業務をお任せできるかのイメージがつかず、社内業務とのマッチングが課題であったため、ハローワーク等の職員が定期的に事業所を訪問し、本人ができる仕事内容と病院側の任せたい業務を具体的にすり合わせて、活躍イメージを双方に持つことができるよう支援を行いました。
支援者のサポートもあり、トライアル雇用終了後は事務職として継続して働いています。
設備工事業での事例
設備工事業のある企業では、本社から障害者雇用の指示を受けたものの、過去に障害者を雇用した際に早期離職となったことや配属予定の部署の担当者が障害者との関わりが初めてであることに不安を抱えていました。
そこで、トライアル雇用を活用し、対応できる業務と職務内容について本人と具体的に調整を行いました。また、ジョブコーチから障害特性と対応方法についてのアドバイスをもらうことで、担当者や他の従業員も障害特性や対応のポイントについて理解を深めることができました。
トライアル雇用を通じて受け入れ体制を整備できたことで、パート勤務で継続雇用となり、今後お任せする業務を拡大していく方向についても、双方の方針が合致し、前向きな方針を決めることができました。
障害者トライアル雇用に関するよくある質問

ここからは、障害者トライアル雇用に関するよくある質問について紹介します。
トライアル雇用中の社会保険・雇用保険の扱いは?
障害者トライアル雇用中でも、労働時間や労働日数など一定の条件を満たす場合は社会保険・雇用保険の加入義務が発生します。障害者短時間トライアル雇用では、週の労働時間が20時間未満のケースもあるため、社会保険等の加入が免除されるケースもあります。
テレワークの場合もトライアル雇用はできる?
障害者トライアル雇用は、テレワークでも利用可能です。ここでのテレワークの定義としては、「対象労働者の1週間の所定労働時間の2分の1以上、情報通信技術を活用して勤務していること」になります。
障害特性により通勤が困難な方や在宅勤務を希望する方は非常に多く、テレワークを希望する求職者ニーズは今後も高まることが予想されています。
しかし、企業ごとに異なるテレワーク環境に適応できるか見極めるには3ヶ月では期間が足りない場合があるという考え方から、原則3ヶ月のトライアル雇用期間を最長6ヶ月まで延長できます。なお、精神障害者の方の場合は、テレワーク以外の場合でも原則6〜12ヶ月間であるため、期間に変更はありません。
また、支給額や支給期間についてはテレワーク以外の場合と変更はありません。
障害者トライアル雇用のポイントを押さえて採用をすすめよう
障害者トライアル雇用は、トライアル期間中に実際の職場で原則3ヶ月はたらくことで、適性や能力を見極め、継続的な雇用を目指す制度です。
定着率に期待ができたり、助成金の利用による採用コストを削減できたりするなどのメリットがあります。
一方で、面接対応の工数が増える可能性や募集の時点で「トライアル雇用専用求人」として求人票を出す必要性があります。求人数を超えたトライアル雇用はできないなどのデメリットや注意点もあるため、十分な採用計画を立てた上で利用することが重要です。
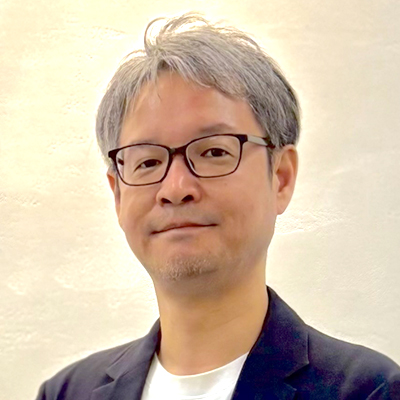
◆監修者
パーソルダイバース株式会社
法人マーケティンググループマネジャー
安原 徹
◆経歴
新卒でベンチャー系コールセンター会社に入社し、営業およびスーパーバイザー業務に従事。その後、株式会社エス・エム・エスにて看護師の人材紹介業務および医療・社会福祉法人の営業を担当。2016年にパーソルダイバース株式会社に入社し、キャリアアドバイザーおよびリクルーティングアドバイザー(RA)として勤務。関西エリアにおける精神障害のある方のご支援先の開拓に注力。2021年に関西RAマネジャーに着任。2023年より中部・西日本RAマネジャーを経て、現在は法人マーケティンググループのマネジャーとして勤務。