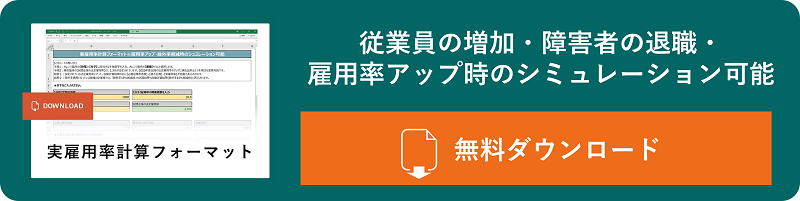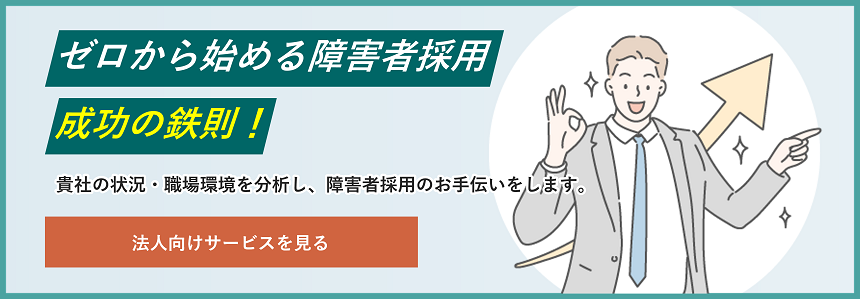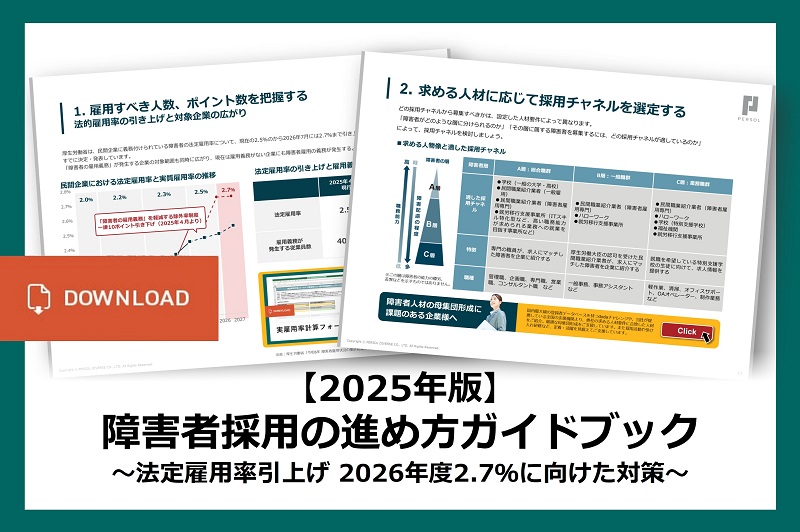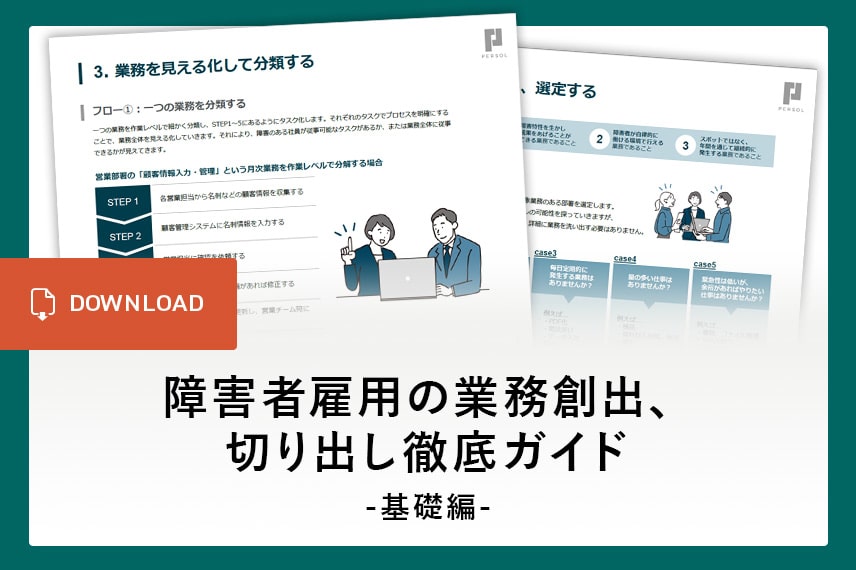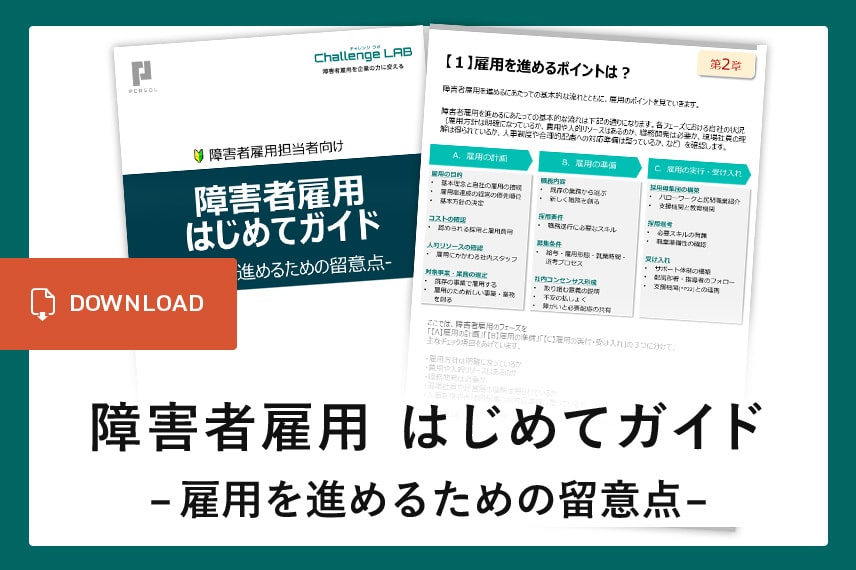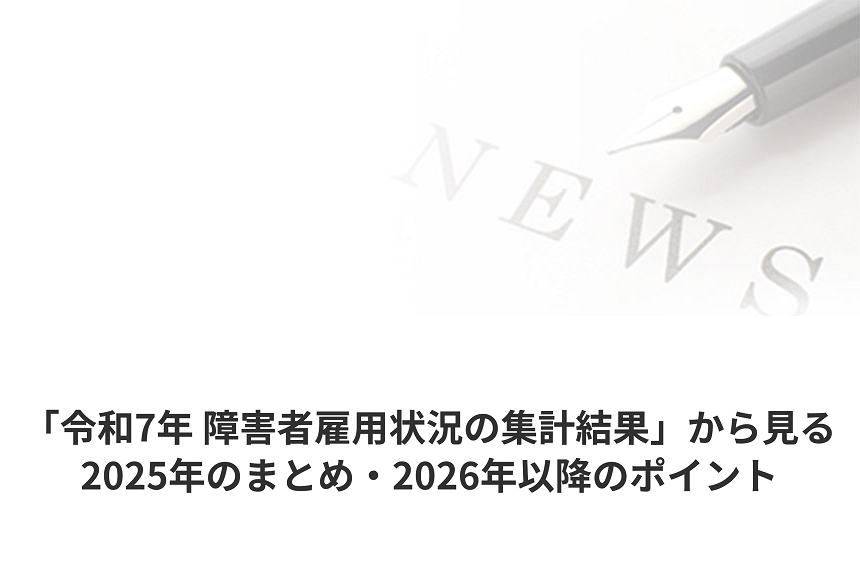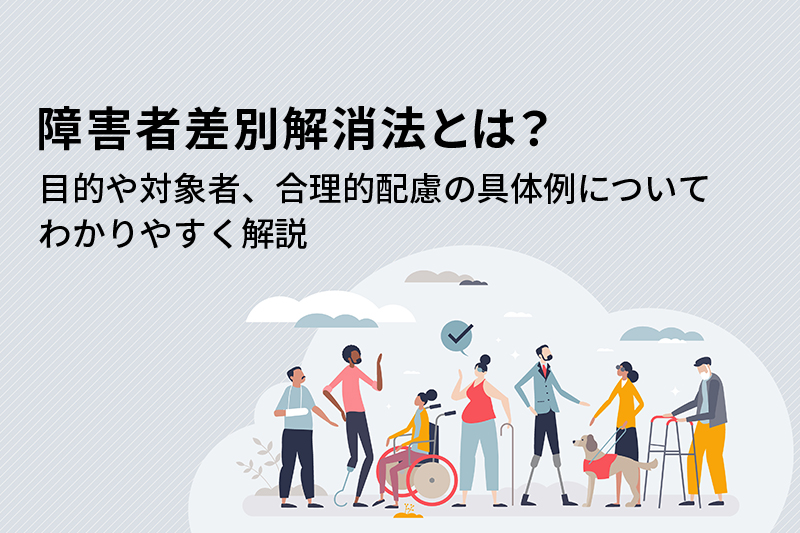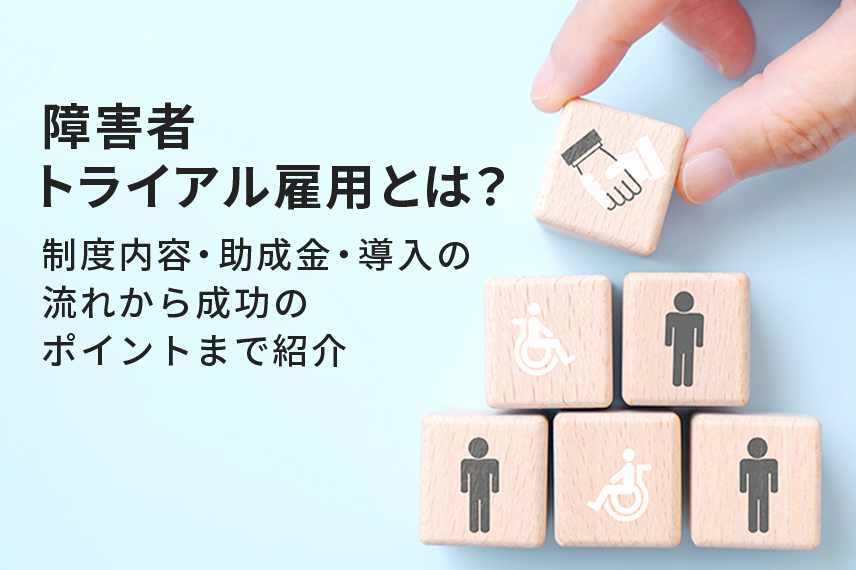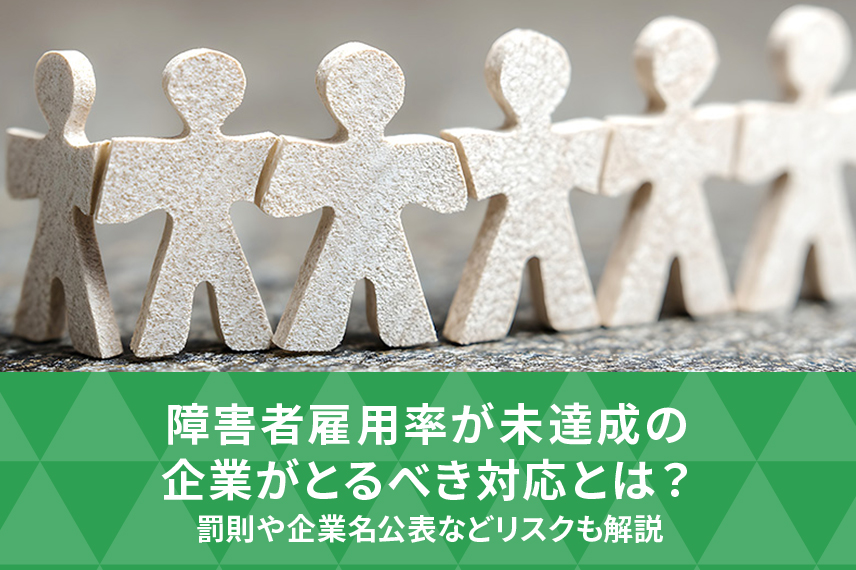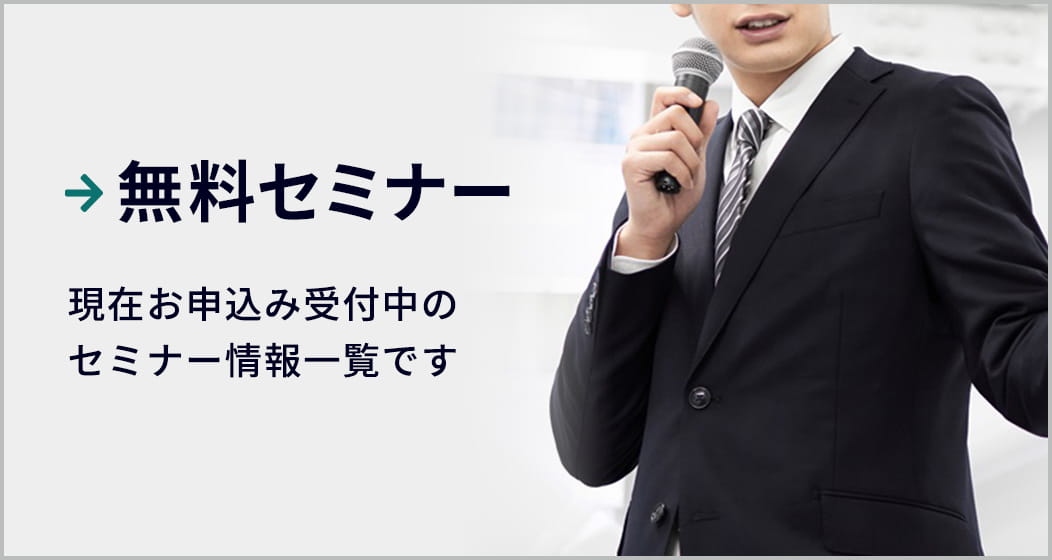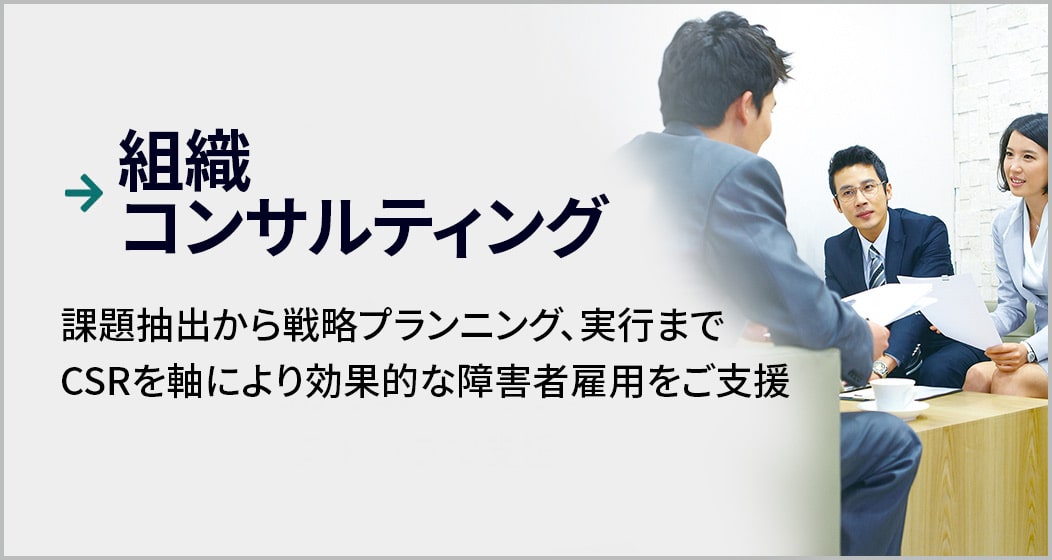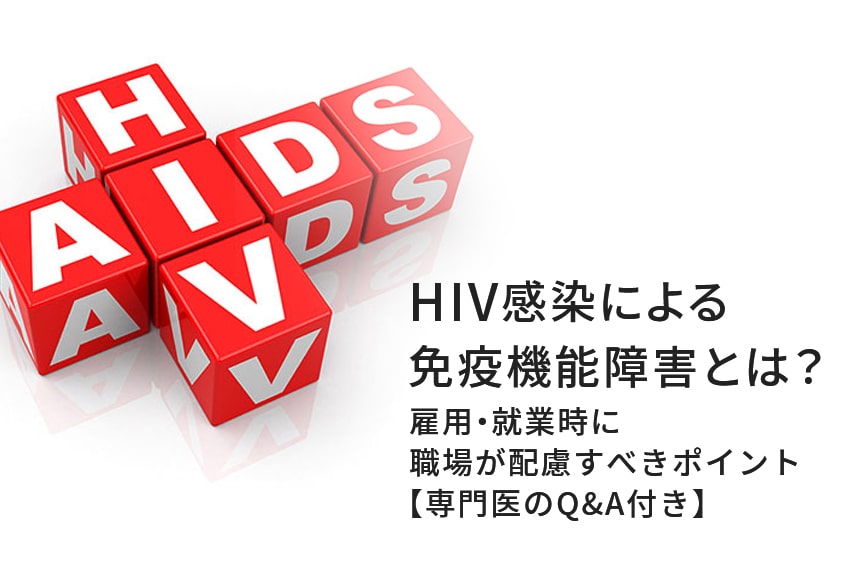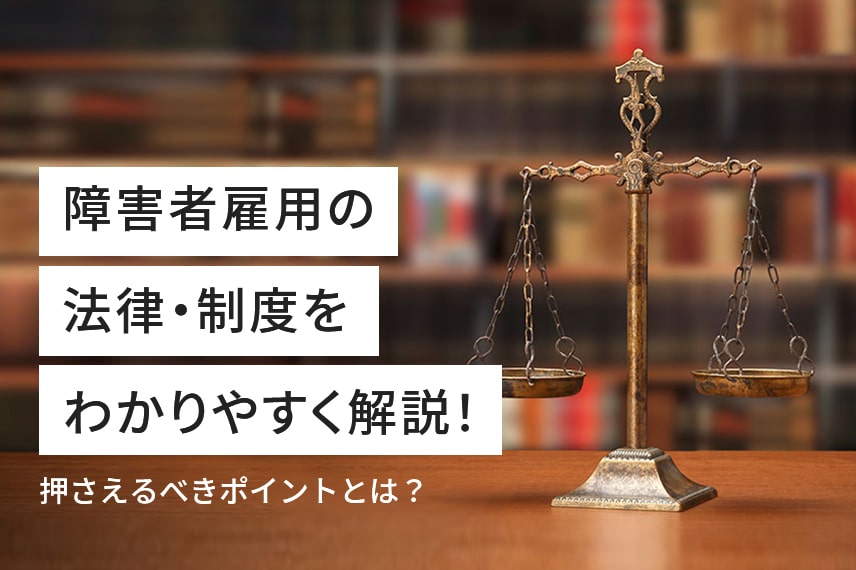- 目次
-
作成日:2025年11月17日
障害者雇用を進める企業の中には、障害者雇用状況報告書の記入方法が分からないという担当者も多いのではないでしょうか。障害者雇用状況報告書とは、一定の企業において毎年厚生労働省に提出することが義務付けられているもので、円滑に障害者雇用を進めるために欠かせません。
本記事では、報告書を作成する企業の担当者に向けて、記入方法や提出方法など、押さえておきたいポイントを詳しく解説します。自社の雇用実態や雇用率達成状況などを正確に報告するために、ぜひ参考にして下さい。
障害者雇用状況報告書とは?

障害者を雇用する一定の企業には、障害者雇用状況報告書の提出が求められます。ロクイチ報告とも言われており、毎年6月1日現在で雇用している障害者数などを報告するものです。
該当する企業は、障害者雇用状況報告書の概要や記入が必要な項目について理解しておくことが大切です。
毎年提出が義務付けられている障害者の雇用状況に関する報告書
障害者雇用状況報告書とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」に基づき、企業が厚生労働大臣へ毎年提出することを義務付けている報告書のことです。
報告義務の対象は、企業全体の常用雇用労働者が原則40人以上の事業主です。記載項目に関しては後述しますが、企業は、毎年6月1日現在で雇用する身体・知的・精神障害者の数を記載します。雇用する障害者数が0人でも提出義務が生じる点に注意が必要です。
また、2026年度からは法定雇用率が2.7%に引き上げられることから、常用労働者が37.5人以上の事業主が対象となります。なお、法定雇用率の引き上げタイミングは2026年7月予定であるため、2026年6月1日にて、まとめる障害者雇用状況報告書は、40人以上の事業主のままである点にも注意が必要です。
障害者雇用報告書を作成する目的は、障害者の雇用実態や法定雇用率の達成状況の把握です。未提出、あるいは虚偽の申告が発覚すると、30万円以下の罰金の対象となります。
障害者雇用状況報告書で記入する主な内容
障害者雇用を進める企業は、事前に記入内容の概要を押さえておくことをおすすめします。記入項目は、以下の通りです。
<記入する主な項目と内訳>
- 事業主:法人名称、氏名または代表者氏名、法人番号
- 雇用の状況:適用事業所番号、事業所の名称・区分・所在地、事業の内容、除外率、常用雇用労働者数、常用雇用身体障害者・知的障害者・精神障害者の数、実雇用率
その他、以下の項目があります。
<その他の項目と内容>
- 「障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数」(特定の身体障害者の種類ごとの人数)
- 「障害者雇用推進者」(障害者雇用を推進する担当者の役職名や氏名)
- 「記入担当者」(記入者の所属部課名や氏名)
障害者雇用状況報告書の提出方法と提出期限

毎年、報告時期になると従業員40人以上規模の企業に報告用紙が送付されます。障害者雇用を進める企業は、期限内に必要事項を記載して提出する必要があります。
ここでは、障害者雇用状況報告書の提出方法と期限について解説します。
提出方法
報告書の提出方法には、郵送または持参する方法と、電子申請があります。
郵送または持参
6月1日現在の雇用状況を企業の主たる事業所(本社)において、支社と支店などの分を取りまとめて、本社の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)あてに、郵送または直接持参して提出します。
3枚複写となっているため、正と副の2枚をハローワークに提出し、企業の控えは保管しておきましょう。記入要領などを確認した上で、正確に記載して下さい。
送付される報告用紙に記載する方法の他、厚生労働省のWebサイトからダウンロードして対応することも可能です。
電子申請
デジタル庁が運営するe-Govにて、所定のエクセルに入力して電子申請を行うこともできます。電子申請の際は、GビズIDまたは、e-Govアカウントを使用した電子署名が必要です。GビズID申請や取得手続きの概要に関しては、デジタル庁のホームページを確認して下さい。
提出期限
報告書の提出期限は、7月15日です。未提出、あるいは虚偽の申告が発覚した場合には罰金の対象となります。6月1日時点の雇用状況を報告することになるため、報告書の記載にかけられる期間は2ヶ月足らずとなります。提出期限内に必要な内容を記載して提出するために、事前に必要な項目と内容を把握しておくことをおすすめします。
障害者雇用状況報告書を記入する前に把握しておくこと
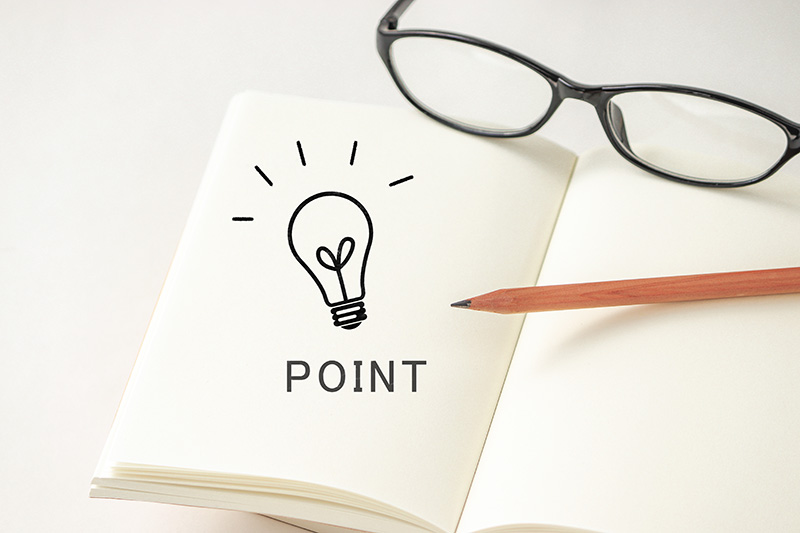
障害者の雇用状況や雇用率の達成状況といった企業が報告するデータは、ハローワークが助言や指導、調査などを実施していくための基本情報として活用されます。障害者雇用を進める企業は、法を遵守し、報告書に正しく記入しなければなりません。
ここでは、企業が迅速かつ正確に報告書を作成するために、押さえておくべきポイントを解説します。
一定規模の企業には障害者雇用義務がある
障害者雇用とは、「障害者雇用促進法」に定められた制度のことで、心身に障害を抱える人が、企業の一般雇用とは別枠ではたらくことです。狭義としては、法定雇用率達成のために条件を満たす障害者を雇用することと定義されます。
一定規模の従業員数を雇用している企業には、障害者雇用が義務化されており、2025年時点では常用雇用する従業員40人以上の企業に対して法定雇用率2.5%の達成が求められています。
障害者雇用制度の目的は、障害の有無にかかわらず、個々人が持つスキルや希望に合わせた仕事を通して活躍できる社会の実現です。
障害者雇用を進める企業は、制度の目的や趣旨を理解しておく必要があります。こちらの記事では、障害者雇用の制度概要やメリット、進め方などに関して詳しく解説しています。
特定業種には除外率が設定されている
障害者雇用状況報告書を作成する際は、除外率の対象となる業種かどうかを確認する必要があります。除外率とは、障害者の就業が一般的に困難と認められる業種について、雇用労働者数計算の際に除外率に相当する労働者数を控除して、障害者の雇用義務を軽減する制度のことです。
厚生労働省が公表している、2025年4月以降の除外率設定業種と割合は以下の通りです。
<除外率設定業種と割合>
| 除外率設定業種 | 除外率 |
|---|---|
|
5% |
|
10% |
|
15% |
|
20% |
|
25% |
|
30% |
|
35% |
|
40% |
|
45% |
|
50% |
|
70% |
除外率の設定に該当する業種については、報告書の「除外率」の欄に割合を記入します。 ただし、除外率制度は廃止が決定しており、段階的に引き下げられ縮小することとされています。障害者雇用状況報告書を作成する際に、前年度分を参照する際は注意が必要です。
障害者数のカウント方法
報告書に障害者数を記載する際は、厚生労働省が公表している以下のカウント方法を理解しておく必要があります。
<障害者数のカウント方法>
| 週所定労働時間 | 30H以上 | 20H以上30H未満 | 10H以上20H未満 | |
| 身体障害者 | 1 | 0.5 | ー | |
| 重度 | 2 | 1 | 0.5 | |
| 知的障害者 | 1 | 0.5 | ー | |
| 重度 | 2 | 1 | 0.5 | |
| 精神障害者 | 1 | 1(※) | 0.5 | |
※当分の間の措置として、精神障害者である短時間労働者は、雇入れの日からの期間等にかかわらず、1人をもって1人とみなすこととしている。
上記の表にある通り、週30時間以上勤務する障害のある労働者は、1人としてカウントされます。ただし、重度の身体障害者または重度の知的障害者については、週30時間以上勤務している場合、2人分としてカウントされます。
週20時間以上30時間未満の短時間勤務の障害者は、0.5人としてカウントされます。ただし、重度の身体障害者または重度の知的障害者で短時間勤務(週20時間以上30時間未満)の場合は、1人分としてカウントされます。
精神障害者で週20時間以上30時間未満勤務する労働者については、通常は0.5人としてカウントされますが、当分の間、1人を1人分としてカウントする特例措置が適用されています。
障害者雇用状況報告書の記入時に注意しておきたい項目
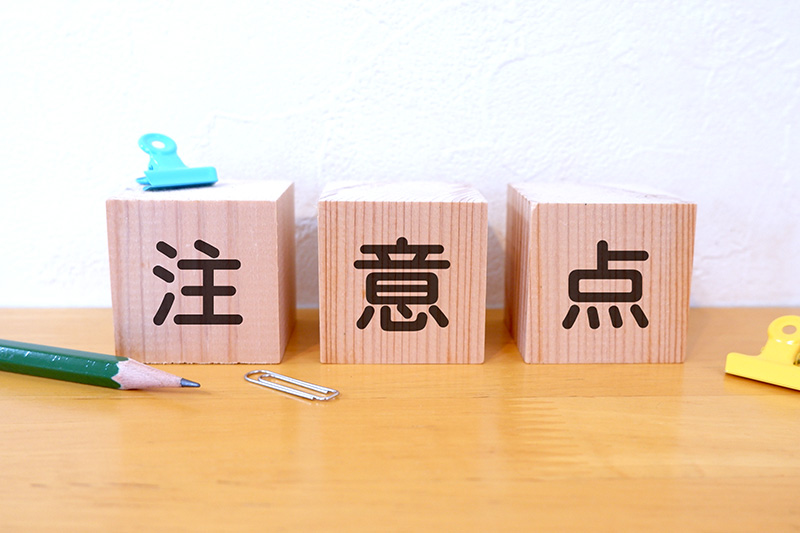
報告書を作成する際は、必ず厚生労働省が提示している「障害者雇用状況報告書及び記入要領等」を確認しましょう。また迅速かつ正確に記載するためには、いくつか注意点を押さえておく必要があります。
ここでは、以下の項目における記入時の注意点を紹介します。
- 常用雇用労働者数
- 障害者数
- 身体障害者、知的障害者又は精神障害者の不足数
常用雇用労働者数
注意したい項目の一つ目は、常用雇用労働者数です。
報告書では、「常用雇用労働者の数」は以下のように区分されています。
<「常用雇用労働者の数」の区分と概要>
(イ) 常用雇用労働者数(短時間労働者を除く):週の所定労働時間が30時間以上の労働者の数
(ロ) 短時間労働者:週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者の数(0.5人として換算)
(ハ) 常用雇用労働者数:(イ)欄に記入した数と(ロ)欄で記入した数に0.5倍した数を合算した数
(ニ)法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数
(ニ)欄の記入内容は、除外率の可否によって異なります。除外率が適用されない企業の場合、(ハ)欄に記入した数と同じ数を記入します。除外率が適用される場合は、以下の計算式で求めた数を記入します。
(ハ)常用雇用労働者数-(ハ)常用雇用労働者数×除外率(端数切り捨て)
障害者数
「常用雇用身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数」の項目には、前述したカウント方法に従い、本社や支店ごとに雇用障害者の数を記入します。項目ごとに障害種別と障害者数を記載したら、障害者数の合計を記載する欄に、算出した身体障害者や知的障害者、精神障害者の合計人数を記入します。
身体障害者、知的障害者又は精神障害者の不足数
障害者数を記入したら、「実雇用率」を基に、企業が法定雇用率を満たしているかどうかを確認します。この時、法定雇用率を下回る場合は、「身体障害者、知的障害者又は精神障害者の不足数」を算出します。
<「実雇用率」の計算式>
実雇用率=障害者数の合計÷「法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者数」×100)
<「身体障害者、知的障害者又は精神障害者の不足数」の計算式>
不足数=(「法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者数」×法定雇用率)−障害者数の合計
よくある質問

ここまで、障害者雇用を進める企業に向けて、報告書の作成方法について解説してきました。しかし、報告書を実際に作成するとなると、前提となる障害者雇用制度に関する深い理解が欠かせません。
ここでは、障害者雇用に関するよくある質問をまとめました。
障害者雇用率を満たさなかったらどうなる?
常用労働者が100人を超える企業が、障害者雇用率を満たさなかった場合は、障害者雇用納付金が徴収されます。納付額は、不足1人当たり月額50,000円です。
なお、障害者雇用は法定義務であるため、納付金を徴収されても雇用免除とはなりません。未達成企業のうち、一定の条件に該当する場合は、雇入れ計画作成命令が発出されます。また、雇入れ計画の期間が満了し、指導が入っても改善されない場合は企業名が公表される場合もあります。
障害者雇用状況報告と混同されがちな障害者雇用納付金との違いは?
障害者雇用状況報告と混同されがちな制度として、障害者雇用納付金制度があります。二つとも、障害者の雇用人数や労働時間を計算し、申告する必要があるという点で混同されやすいと言われています。
前述の通り、障害者雇用状況報告は、国が企業の雇用状況や雇用率の達成状況を把握することで、各企業に対する障害者雇用の施策検討などに役立てるものです。
障害者雇用納付金制度は、法定雇用率を達成できなかった企業から納付金を徴収した上で、雇用達成した企業の中で、常時雇用している労働者数が100人以下で一定の条件を満たし、申請した企業については報奨金が支給されるという制度を指します。
障害者雇用状況報告は、ハローワークへ申告するものであるのに対し、納付金に関する申告は高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)に行います。
障害者雇用に関する相談先・支援先は?
障害者雇用を円滑に進めていくためには、適切な専門機関からの支援が有用です。
障害者雇用についての主な相談先・支援先には以下が挙げられます。
<障害者雇用に関する相談先・支援先>
- ハローワーク:障害者を対象として求人の申し込みの受付け
- (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構:障害者の雇用支援に関する相談窓口やイベント・セミナーの開催や調査研究など
- 障害者就業・生活支援センター:障害者の身近な地域にて、関係機関と連携の上、就業面や生活面での一体的な相談支援
各機関によって、対応可能な範囲が異なります。自社の状況や課題を考慮して、支援を受けることをおすすめします。
障害者雇用を企業が独自に進めるとなると、多くの困難に直面することがあります。就労したいと考える障害者の適性を見極め、定着させていくためには、自社の状況や職場環境を分析していくことが不可欠です。
まとめ
本記事では、障害者雇用を進める企業の担当者に向けて、障害者雇用状況報告書の作成方法について解説しました。障害者雇用状況報告書とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」に基づき、毎年6月1日時点の雇用実態について、企業に対して厚生労働大臣へ毎年提出することを義務付けている報告書のことです。報告書の作成は、障害者の雇用実態や法定雇用率の達成状況の把握を目的としています。
そもそも障害者雇用は、障害者が自身の能力や希望に合う仕事ではたらくことができる社会の実現を目的として定められている制度であり、一定の企業で義務化されています。
社会全体で障害者雇用を円滑に進めていくために、企業としては期限内に適切な方法で報告書を作成する必要があります。本記事で解説した作成方法や注意点を押さえた上で、就労を希望する障害者と企業の双方にとって、はたらきやすい環境の構築を目指していきましょう。
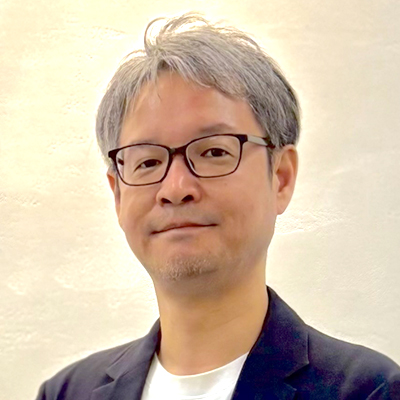
パーソルダイバース株式会社
法人マーケティンググループマネジャー
安原 徹
新卒でベンチャー系コールセンター会社に入社し、営業およびスーパーバイザー業務に従事。その後、株式会社エス・エム・エスにて看護師の人材紹介業務および医療・社会福祉法人の営業を担当。2016年にパーソルダイバース株式会社に入社し、キャリアアドバイザーおよびリクルーティングアドバイザー(RA)として勤務。関西エリアにおける精神障害のある方のご支援先の開拓に注力。2021年に関西RAマネジャーに着任。2023年より中部・西日本RAマネジャーを経て、現在は法人マーケティンググループのマネジャーとして勤務。