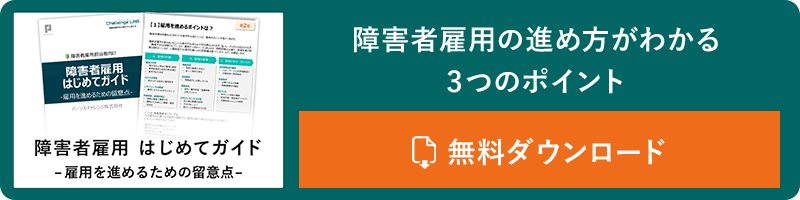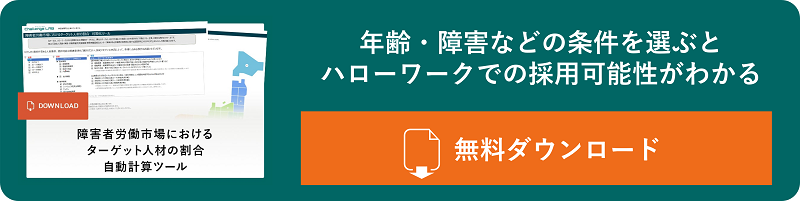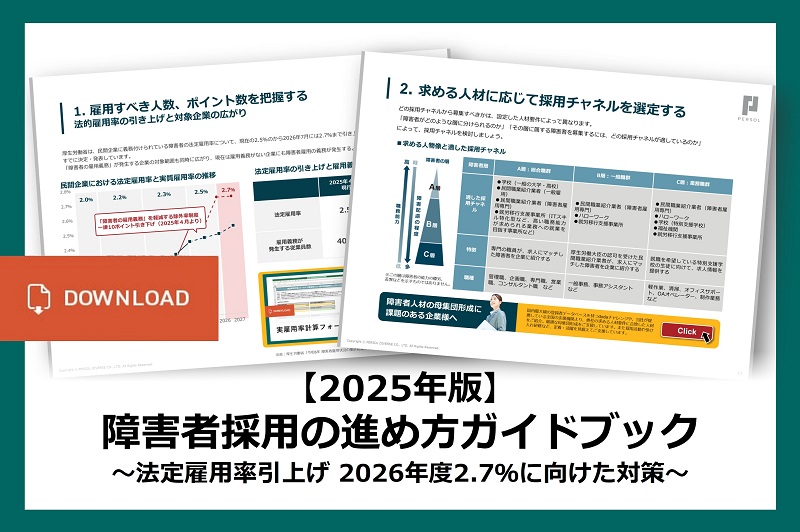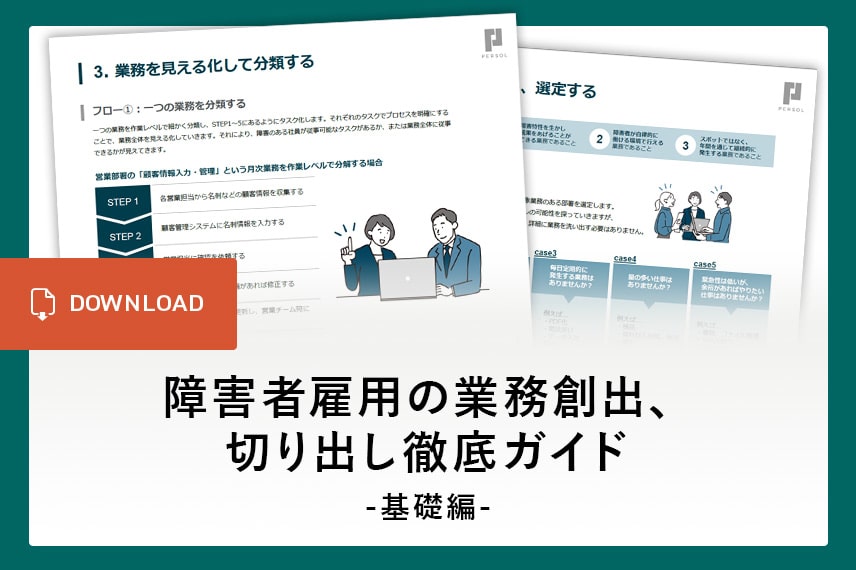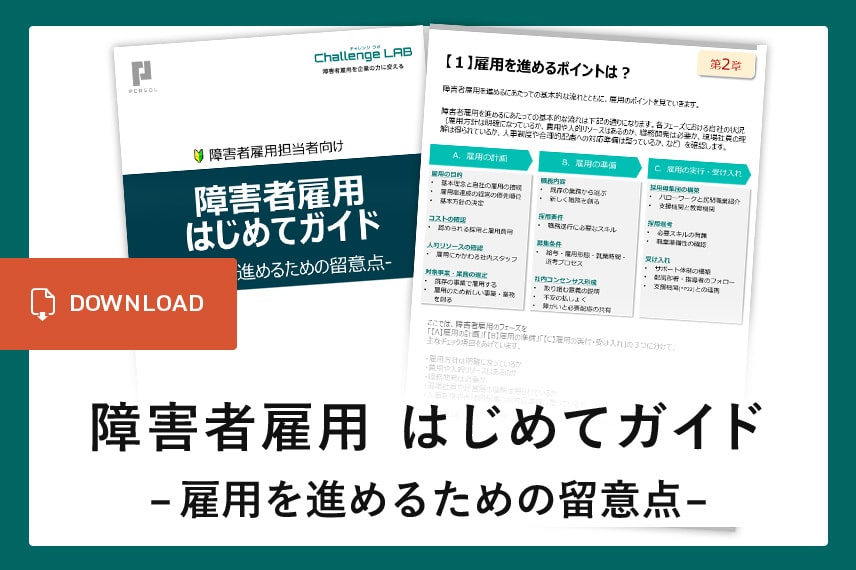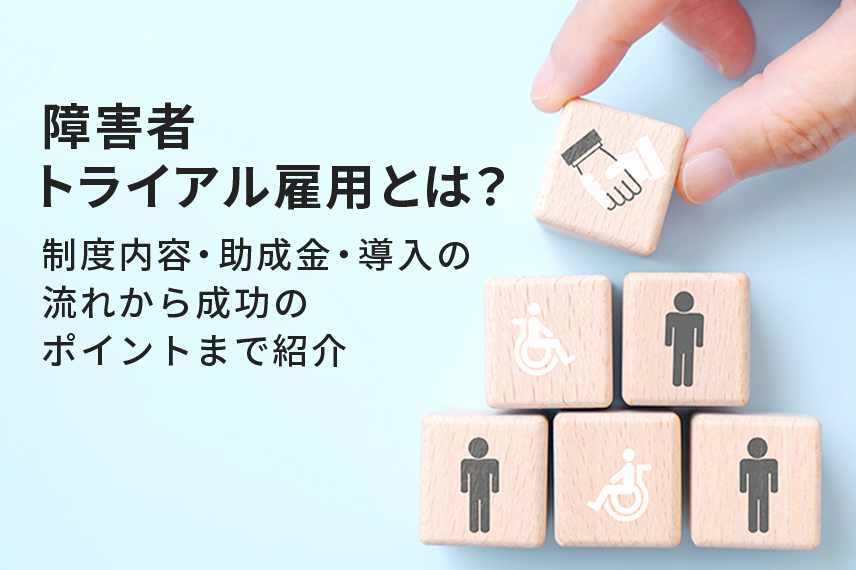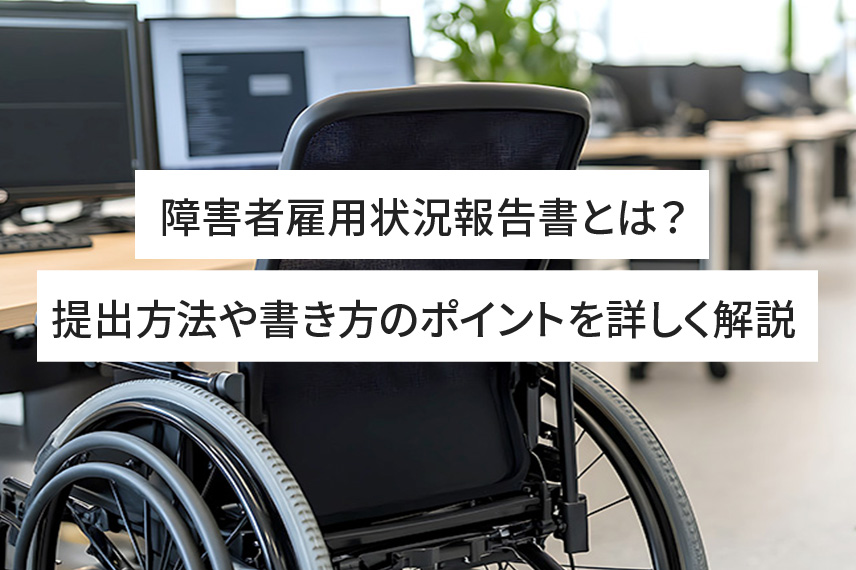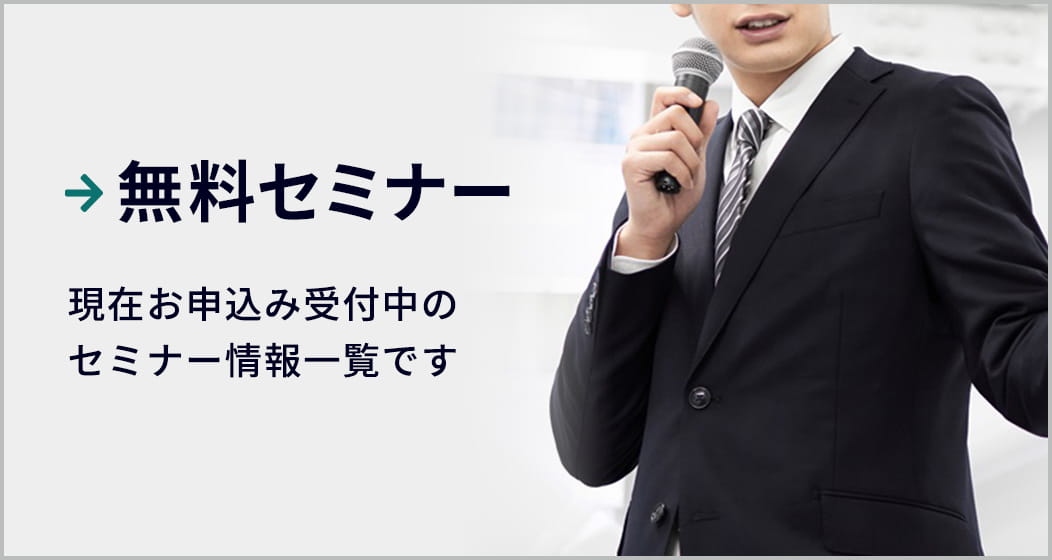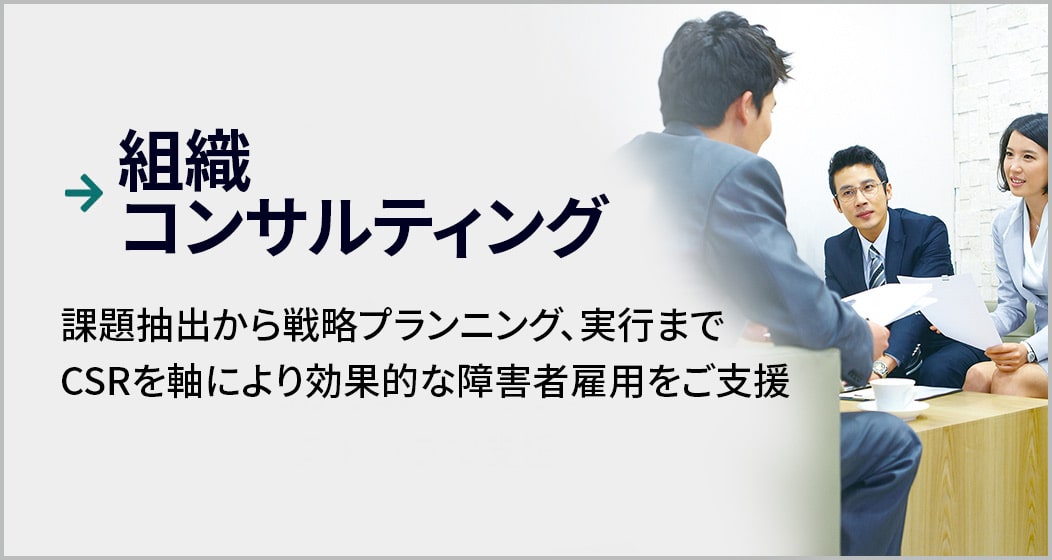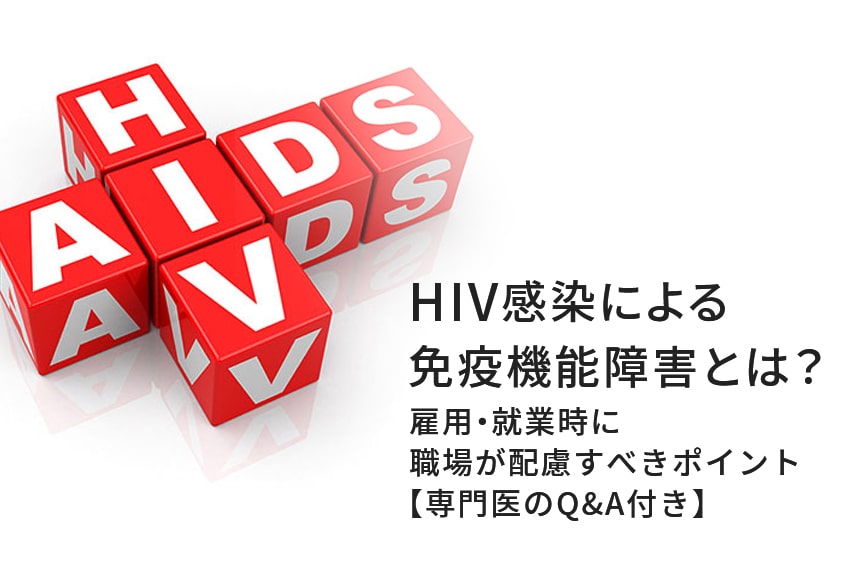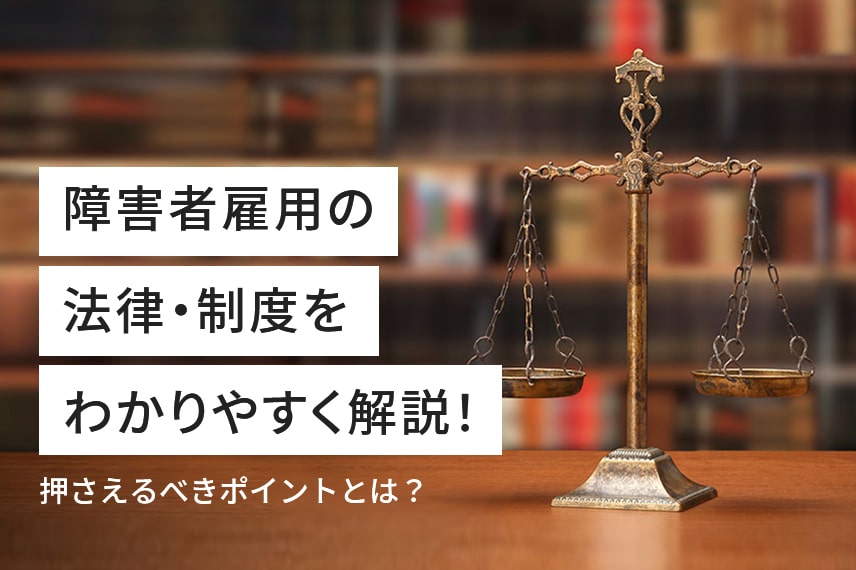- 目次
-
作成日:2025年11月17日
障害者雇用率はここ数年で上昇しているため、雇用率の達成に課題を感じている企業も少なくありません。障害者雇用率が未達成の場合、障害者雇用納付金の徴収が行われるだけでなく、状況が改善しなければ行政指導や企業名の公表に発展する場合もあります。
本記事では、障害者雇用率が未達成の場合の罰則やリスク、未達成の企業がとるべき対応について解説します。
障害者雇用率とは?基本と最新の法定ルールをおさらい

障害者雇用率の未達成について考える前に、まずは障害者雇用率制度の基本をおさらいしておきましょう。
障害者雇用率制度(法定雇用率)の定義と背景
障害者雇用率制度(法定雇用率)とは、企業が一定割合の障害者を雇用することを法律で義務づけた制度です。「障害者雇用促進法43条第1項」に基づき、従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める障害者の割合を障害者雇用率以上にする義務があります。
障害者雇用率制度は、障害者が一般労働者と同様に、安定的かつ継続的に雇用される機会を確保することを目的としています。
現在の障害者雇用率(法定雇用率)と改定内容
2025年時点での障害者雇用率は、民間企業は2.5%、国・地方公共団体は2.7%ですが、2026年(令和8年)7月からそれぞれ2.7%と3.0%に上がります。
また、独立行政法人などの特殊法人、都道府県等の教育委員会についてはそれぞれ障害者雇用率が下記の表のように異なります。
| 2026年6月まで | 2026年7月以降 | |
|---|---|---|
| 民間企業 | 2.5% | 2.7% |
| 特殊法人等 | 2.8% | 3.0% |
| 国、地方公共団体 | 2.8% | 3.0% |
| 都道府県等の教育委員会 | 2.7% | 2.9% |
対象となる企業規模と業種別の違い
2025年現在は、対象となる民間企業の範囲は、常用雇用労働者数40.0人以上の事業主です。2026年(令和8年)7月からは常用雇用労働者数37.5人以上の事業主が対象となります。
障害者雇用率をもとに雇用義務がある人数を計算するには、下記の計算式を活用します。
- 法定雇用障害者数=(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×法定雇用率
例えば、常用労働者数が90人、短時間労働者数が10人の民間企業の場合は、下記のように計算できます。
(90+10×0.5)×2.7%=2.565人
小数点以下は切り捨てになるため、2人以上の障害者雇用義務があることが分かります。
障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種については、労働者数を控除する「除外率制度」が設けられています。除外率制度は、2004年(平成16年)4月に廃止されましたが、経過措置として、当面の間、廃止の方向で段階的に除外率を引き下げ、縮小することになっています。
カウント対象となる「障害者」の範囲とは
障害者雇用率の対象となるのは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所有者です。
基本的には、週所定労働時間30時間以上の常用労働者を1人とカウントし、20時間以上30時間未満の短時間労働者は0.5人とカウントします。
ただし、重度の身体障害者と重度の知的障害者については、30時間以上の場合は2人、20時間以上30時間未満の場合は1人、そして10時間以上20時間未満の場合は、0.5人となります。
また、精神障害者の場合は、20時間以上30時間未満の場合は1人、10時間以上20時間未満の場合は0.5人とカウントします。
| 30時間以上 | 20時間以上30時間未満 | 10時間以上20時間未満 | |
|---|---|---|---|
| 身体障害者 | 1 | 0.5 | - |
| 知的障害者 | 1 | 0.5 | - |
| 精神障害者 | 1 | 1 | 0.5 |
| 身体障害者(重度) | 2 | 1 | 0.5 |
| 知的障害者(重度) | 2 | 1 | 0.5 |
障害者雇用率が未達成だとどうなる?罰則と影響
障害者雇用を推進していても、障害者雇用率を達成できない場合もあるでしょう。ここでは、障害者雇用率が未達成である場合の罰則やペナルティとその影響について解説します。
障害者雇用納付金制度とは
罰則やペナルティに関連が深いのが「障害者雇用納付金制度」です。障害者雇用納付金制度とは、障害者雇用の水準を高めることを目的とした制度であり、障害者を多く雇用している事業主の経済的負担を軽減し、事業主間の負担の公平を図るものです。
具体的には、常用労働者100人超の企業で障害者雇用率が未達成の企業から障害者雇用納付金が徴収される仕組みになっています。常用労働者100人以下の企業からは徴収されません。
徴収金額は1人当たり月額5万円となります。例えば、本来10人雇用する義務がある企業が、実際は8人しか雇用できていなかった場合、2人分不足していることとなるため、月10万円を徴収されます。
この徴収された納付金は、障害者雇用率を達成している企業に対して支給する、調整金や報奨金に使われます。常用労働者100人以下の企業は納付金の対象外となりますが、調整金や報奨金の対象にはなります。
行政指導や企業名公表の流れと基準
障害者雇用率が未達成の状況が続くと行政指導が行われたり、企業名を公表されたりするリスクがあります。ただし、未達成であればすぐに行政指導や企業名公表が行われるわけではなく、状況を改善できれば企業名公表などの大きな影響は避けることができます。
行政指導や企業名公表の流れは以下の通りです。
- 雇用状況報告(毎年6月1日の状況)
- 雇入れ計画作成命令(2年計画)
- 雇入れ計画の適正実施勧告
- 特別指導
- 企業名の公表
障害者雇用率が未達成の場合に、初めに行われるのが、「雇入れ計画作成命令」です。雇入れ計画作成命令は、次のいずれかに該当する場合に行われます。
- 実雇用率が全国平均実雇用率未満であり、かつ不足数が5人以上の場合
- 実雇用率に関係なく、不足数10人以上の場合
- 雇用義務数が3人から4人の企業(労働者数120人~199.5人規模企業)であって雇用障害者数0人の場合
該当企業は、雇入れ計画作成命令を受けた場合、翌年の1月1日を始期とする2年間の障害者の雇入れ計画を作成し、実施しなければいけません。障害者の雇入れ計画の実施を怠っている場合などは、公共職業安定所長が雇い入れ計画の適正な実施の勧告をする場合があります。
その後、計画に基づく障害者雇用が進まず、以下の要件に当てはまる場合に特別指導が行われます。
- 実雇用率が最終年前年の6月1日現在の全国平均実雇用率未満(※不足数0人の場合を除く)
- 不足数が10人以上
特別指導を実施しても改善が見られない場合は、企業名が公表されるという流れになります。
なお、企業名公表後も障害者雇入れ計画が終了するまで指導は続き、雇用が進まない場合は再度企業名が公表されます。
障害者雇用率の未達成や企業名公表による社会的影響
障害者雇用率が未達成であることや未達成状態が続き企業名公表されると企業としても大きな社会的影響を受けます。ここでは、主な以下の3つの影響について解説します。
- 企業ブランディングが毀損する
- 株主への説明責任が生じる可能性がある
- 自治体入札への影響が出る場合がある
企業ブランディングが毀損する
企業名が公開されることで、企業ブランディングの毀損につながります。多くの日本企業にとって、競争力強化やイノベーション創出に向け「同質性」の回避が喫緊の課題であり、その観点からダイバーシティ経営推進が不可欠といえます。
企業名の公表により、ダイバーシティ経営に取り組んでいないという評価になり、ブランディングの毀損に繋がります。このような会社としてのメッセージングは、採用ブランディングにも影響し、新卒採用・キャリア採用などにも影響が出るリスクをはらんでいます。
株主への説明責任が生じる可能性がある
企業名が公表されることで、株価に影響が出てしまい、株主への説明責任が生じる可能性があります。さらに、障害者雇用率が未達成の場合、障害者雇用納付金を納付する必要があり、1人当たり年間で60万円(月額5万円×12ヶ月)の損失となります。
社会的イメージの低下や業績悪化によって株価が下がるなどの事態が起これば、株主への影響も避けられません。実際に株主訴訟に発展した過去事例もあります。
自治体入札への影響が出る場合がある
障害者雇用率が未達成であることで、自治体入札への影響が出る場合もあります。実際に大阪府では「大阪府ハートフル条例」を制定しており、入札条件として法定雇用率の達成を定めています。
また、静岡県では県の行う入札・随意契約等において障害者の雇用を積極的に取り組む事業所に対して優遇制度を実施しており、その要件の1つとして障害者雇用率の達成があります。
そのため、障害者雇用率が未達成であることで、自治体入札に参加できない・不利になるといった影響が考えられます。
なぜ未達成になるのか?企業が抱える課題とは

障害者雇用率が未達成の企業が全て障害者雇用に消極的なわけではありません。障害者雇用率を高めたくても、さまざまな要因でうまくいかないこともあります。障害者雇用を推進するための主な課題は以下の2つです。
- 採用の難しさ
- 社内理解・体制不足による定着困難
企業が抱える課題についてそれぞれ解説します。
採用の難しさ
障害者雇用率を高めたくても、採用が難しいという課題があります。障害者雇用市場では、採用対象の母集団が限られており、求める人材になかなか出会えないと悩む企業も多いでしょう。
また、「採用時における適正や能力の把握」や「新たな職域・業務の創出」に課題を感じている企業も多い傾向にあります。
社内理解・体制不足による定着困難
いざ採用できても社内の理解不足や体制の未整備によって、早期離職してしまうこともよくある課題です。
障害への理解が不足しているため、どのような配慮が必要なのかが分からなかったり、どのようにコミュニケーションをとり、マネジメントしていくのか分からないと悩む企業も少なくありません。障害特性は人によって異なるため、必要な配慮事項や対応策もそれぞれ異なる難しさがあります。
また、体制不足や制度の未整備なども課題として挙げられます。「障害者雇用の方の人事制度(雇用条件・評価指標・キャリアパスなど)」や「健康支援・マネジメント」の未整備は定着率の低下につながります。
障害者がはたきやすい環境を整備できていない状況では、せっかく採用できた人材も定着率が低く、早期の離職という結果につながってしまいます。
障害者雇用の課題や成果について下記記事でも詳しく解説しておりますので、ぜひご参考下さい。
障害者雇用率を達成するための改善施策

障害者雇用率を上げていくためには、障害者雇用特有の課題を把握した上で対策を行うことが重要です。障害者雇用率を達成するための主な改善策は以下の3つです。
- 採用チャネルの拡大と支援機関の活用
- 職場環境と業務の設計による定着支援
- 中長期的な雇用計画の立案と評価方法
それぞれの施策について解説します。
採用チャネルの拡大と支援機関の活用
ハローワークや人材紹介会社、特別支援学校や就労移行支援事業所との連携を通じて、採用チャネルの拡大をすることは有効な施策です。
採用チャネルを拡大することで、これまでアプローチできなかった層に自社をアピールでき、多様な人材からの応募が期待できます。
特にハローワークは、障害者雇用において中心的な役割を担っているため、どこに相談して良いか分からないといった場合は、まずはハローワークに相談してみると良いでしょう。
職場環境と業務の設計による定着支援
定着支援を行うことも障害者雇用率を達成するために重要です。定着支援に関する施策を紹介します。
障害特性に応じた業務設計の工夫
障害者がはたらきやすいように、障害特性に応じた業務設計を行いましょう。業務の内容や量を調整するなどの業務上の配慮や業務内容の明確化などが有効です。
また、環境整備も重要です。フレックス制やリモートワーク、短時間勤務など多様なはたらき方ができるように制度を整えましょう。
さらに、通院などのための休暇取得への配慮や休憩時間・休憩場所の配慮などもはたらき方の柔軟性を高め、定着率の向上につながります。
職場内の理解促進とサポート体制構築
障害や障害者雇用についての職場内の理解促進やサポート体制を構築することも重要です。
社内研修やセミナーなどを通じて、障害への理解促進や障害者雇用の目的や意義についての周知を徹底しましょう。また、業務の切り出しやマニュアルの作成など、受け入れ側のサポート体制の構築も同時にすすめていきましょう。
安心してはたらけるように担当者をアサインすることも1つの方法です。「先輩社員がミーティングなどで離席しがち」「多忙そうで話しかけづらい・聞きたいことが聞けない」といった環境では、不安やストレスが増長してしまう可能性があります。
急な体調の変化や日々の不安などを言葉にして伝えるのが苦手な人もいるため、定期的な面談の実施や外部支援機関との連携などを通じて、状態の変化に早めに気付ける体制を整えておくことが重要です。
中長期的な雇用計画の立案と評価方法
障害者雇用率の達成に向けて、中長期的な雇用計画の立案と定期的な評価を行いましょう。
「いつまでに・何人雇う必要があるのか」、そのためには「いつ・何をすべきか」を明確にし、雇用計画を立てます。定期的に雇用計画について評価を行い、必要に応じて計画を修正するなどPDCAを回していくことが大切です。
障害者雇用の促進に活用できる助成金・制度・外部支援

障害者雇用の促進のために活用できる助成金や制度が多くあります。助成金や制度、そして外部支援をうまく活用しながら、障害者雇用をすすめていきましょう。
障害者雇用に関する助成金一覧
障害者雇用を行う際に利用できる助成金は多くあります。主な助成金を表にまとめましたので、ご参考下さい。
| 助成金の種類 | 主な種類 |
|---|---|
| トライアル雇用助成金 |
|
| 継続雇用に対する助成金 |
|
| 継続して雇用する障害者への配慮に対する助成金 |
|
各助成金の内容や申請方法については、下記記事で詳しく紹介しておりますので、助成金について知りたい方はぜひご覧下さい。
社外リソースを活用するメリット
社外のリソースを活用することで、自社だけでは解決が難しい課題についても対策や解決に向けた一歩をすすめやすくなります。特にこれまで障害者雇用の経験が浅く、障害者雇用に不安を抱えている方は、障害者専門の支援サービスの活用がおすすめです。
パーソルダイバース株式会社では、「グループ障害者雇用事業」と「対外支援事業」の2つの領域で事業を展開し、採用計画から採用後の定着支援まで幅広くご支援いたします。特例子会社として自社で障害者雇用を行ってきた当事者経験に基づくノウハウの深さが強みです。
実際の支援内容については下記記事でも詳しく紹介しておりますので、ぜひご確認下さい。
障害者雇用率の未達成に関するよくある質問

ここからは、障害者雇用率の未達成に関するよくある質問について紹介します。
障害者雇用率が未達成の企業の割合はどれくらい?
厚生労働省が発表している「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」によると、障害者雇用率が未達成の企業は54%であり、対前年比4.1ポイント上昇しています。障害者雇用率が前年から0.2ポイント上昇したことにより、全ての企業規模で前年より未達成の企業の割合が増えています。
特に中小企業の未達成の割合が高く、常用労働者数が1,000人以上の企業の未達成の割合は45.3%であるのに対し、40.0〜43.5人未満規模の企業では66.7%、43.5〜100人未満の企業で54.6%になっています。
| 常用労働者数 | 未達成の割合 |
|---|---|
| 40.0〜43.5人未満 | 66.7% |
| 43.5〜100人未満 | 54.6% |
| 100~300人未満 | 50.9% |
| 300~500人未満 | 58.9% |
| 500~1,000人未満 | 55.7% |
| 1,000人以上 | 45.3% |
最新の障害者の雇用状況については、下記記事でも詳しく紹介しておりますので、併せてご確認下さい。
実際に社名が公表された企業や行政指導を受けた企業はどれくらいある?
2023年度(令和5年)の実績では、「雇入れ計画の適正実施勧告」を受けた企業が63社、「特別指導」が実施された企業が33社、企業名の公表は1社でした。
過去5年で企業名が公表された企業数は以下の通りです。
| 年度 | 公表された企業数 |
|---|---|
| 2019年 | 0社 |
| 2020年 | 1社 |
| 2021年 | 6社 |
| 2022年 | 5社(3社が再公表) |
| 2023年 | 1社(再公表) |
障害者雇用率の達成に向けて一歩ずつすすめていこう

障害者雇用率が未達成の状態が続くと、最終的には企業名が公表され、企業イメージの毀損や株主への説明責任にも発展するため、障害者雇用率達成のために適切に対応を行うことが必要です。
障害者雇用率を高めるためには、障害者雇用の課題を理解した上で対策をすすめていくことが重要ですが、自社だけで解決しようとせず、外部リソースをうまく活用することがポイントになります。また、助成金を活用することでコストを削減し、障害者雇用を推進することができます。
ハローワークや障害者専門の支援サービスなどの社外のリソースを活用し、障害者雇用率達成のために一歩ずつすすめていきましょう。
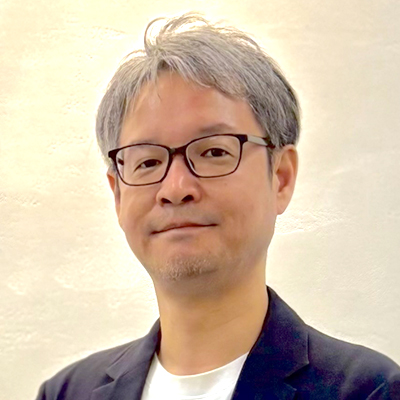
パーソルダイバース株式会社
法人マーケティンググループマネジャー
安原 徹
新卒でベンチャー系コールセンター会社に入社し、営業およびスーパーバイザー業務に従事。その後、株式会社エス・エム・エスにて看護師の人材紹介業務および医療・社会福祉法人の営業を担当。2016年にパーソルダイバース株式会社に入社し、キャリアアドバイザーおよびリクルーティングアドバイザー(RA)として勤務。関西エリアにおける精神障害のある方のご支援先の開拓に注力。2021年に関西RAマネジャーに着任。2023年より中部・西日本RAマネジャーを経て、現在は法人マーケティンググループのマネジャーとして勤務。
関連リンク
- 厚生労働省「障害者雇用率制度について」
- 厚生労働省「障害者雇用率達成指導の流れ」
- 東京労働局「障害者の雇用に向けて」
- 大阪府「【ハートフル条例広報パンフレット】契約の相手方等大阪府と関係のある事業主へのご案内」
- 厚生労働省「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」
- 障害者雇用の除外率制度とは?10%削減・法定雇用率引き上げ影響と今後の対策を提言
- 障害者雇用の成果について、7割が「企業活動に貢献している」と実感
- 障害者雇用の助成金制度~種類・対象・受給額・条件を解説~
- 第1回初めての障害者雇用、企業が持つべき心得とは?
- 「障害者の就職件数、2年連続で過去最高を更新 厚生労働省「令和6年度 障害者の職業紹介状況等」」