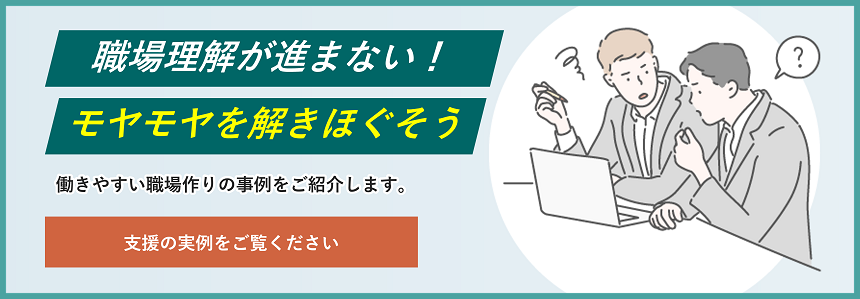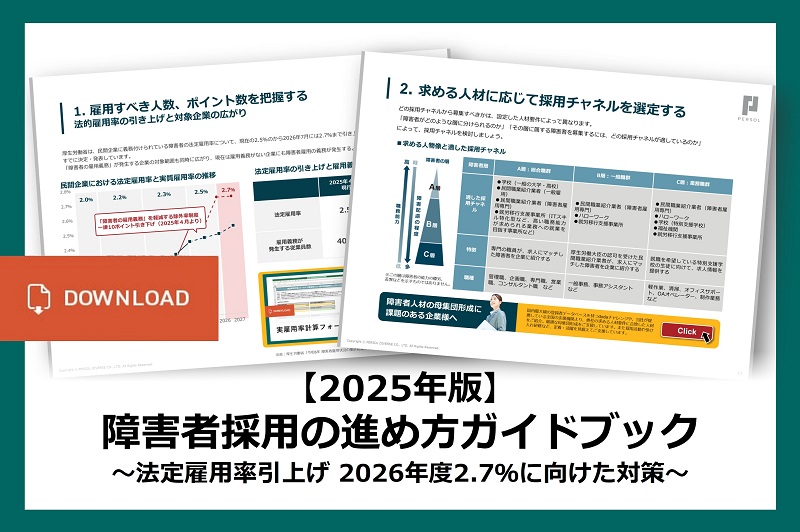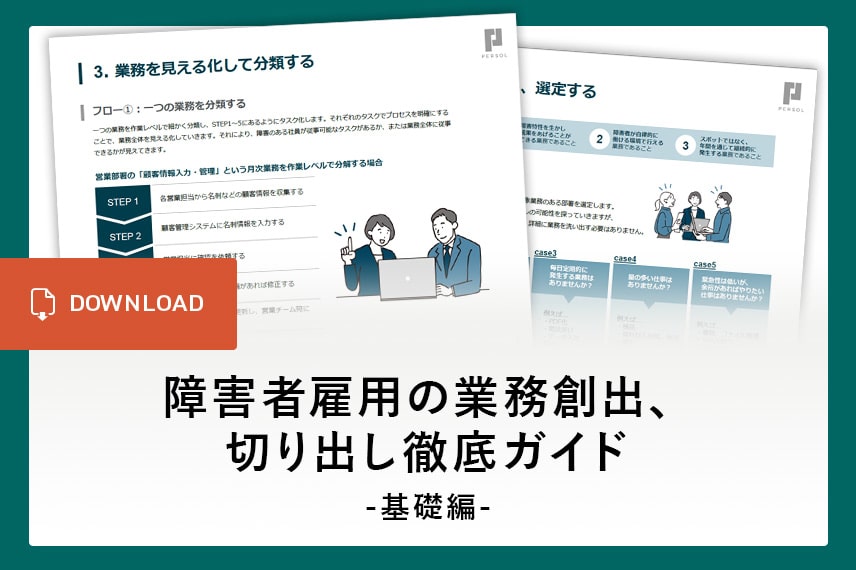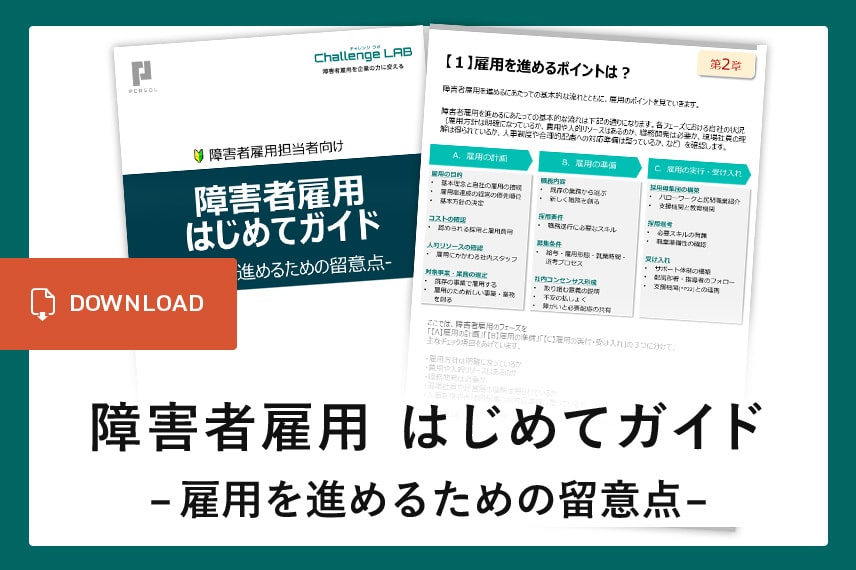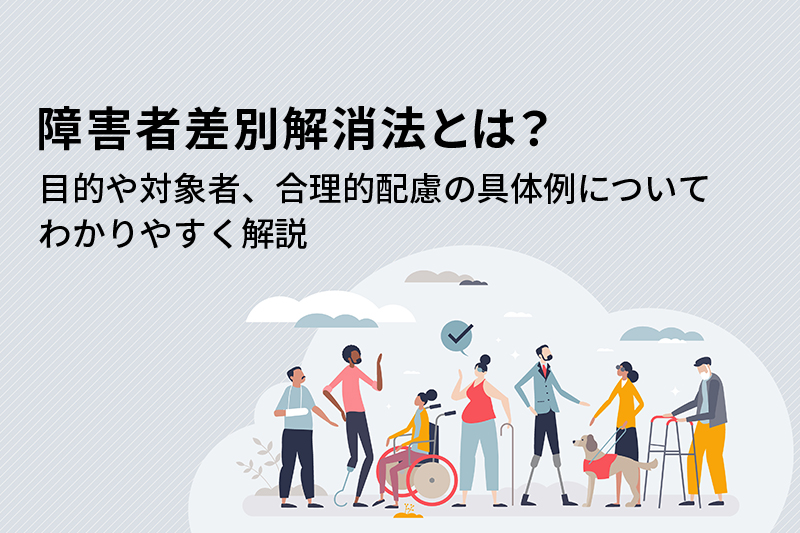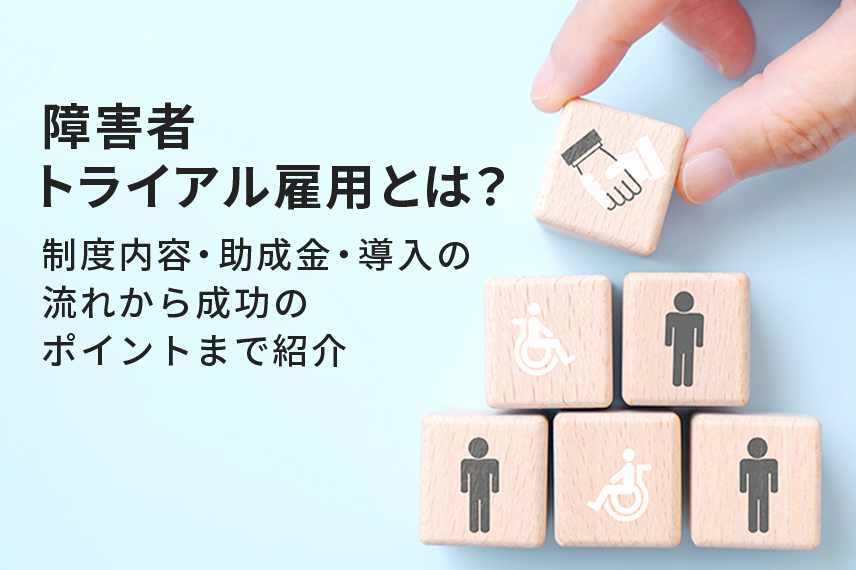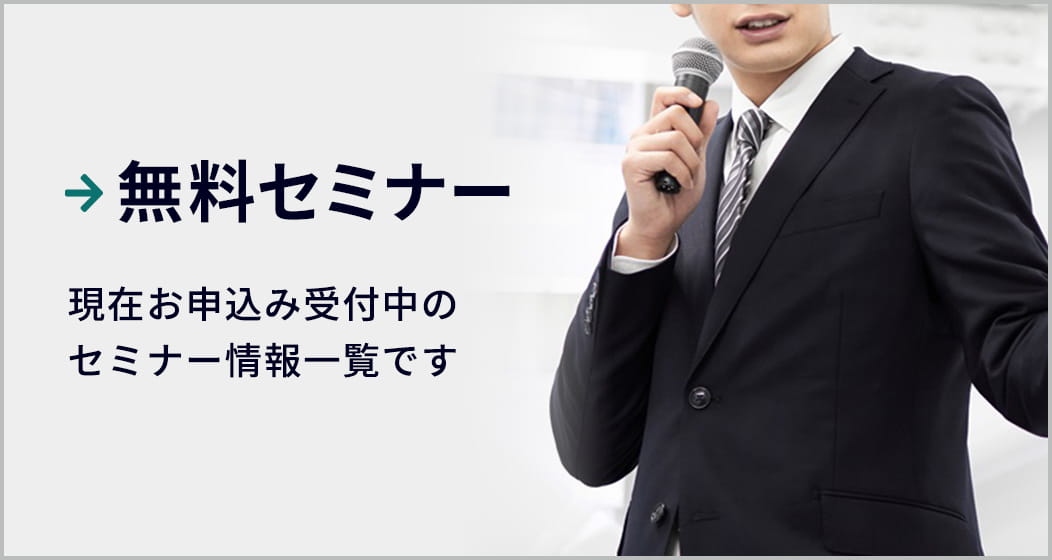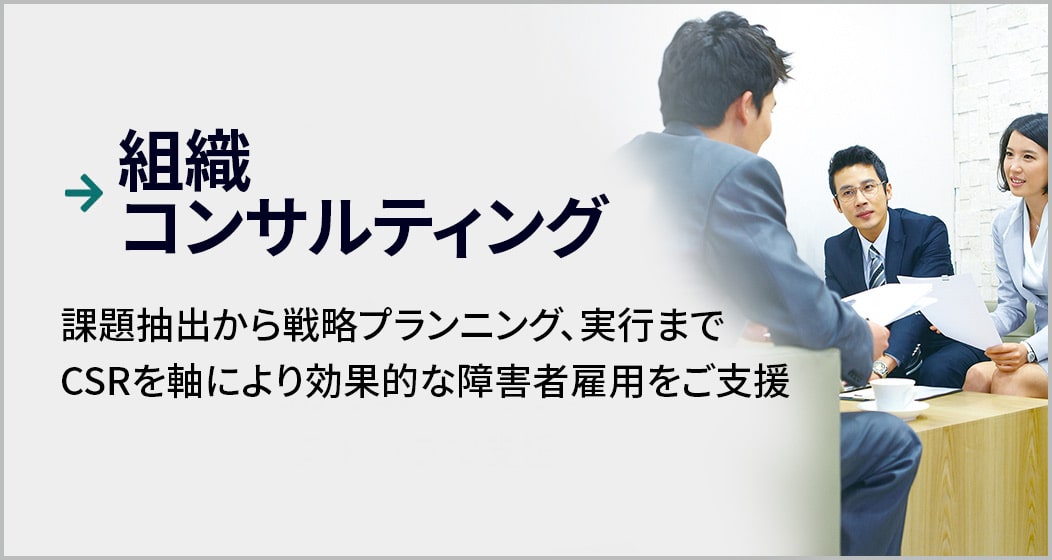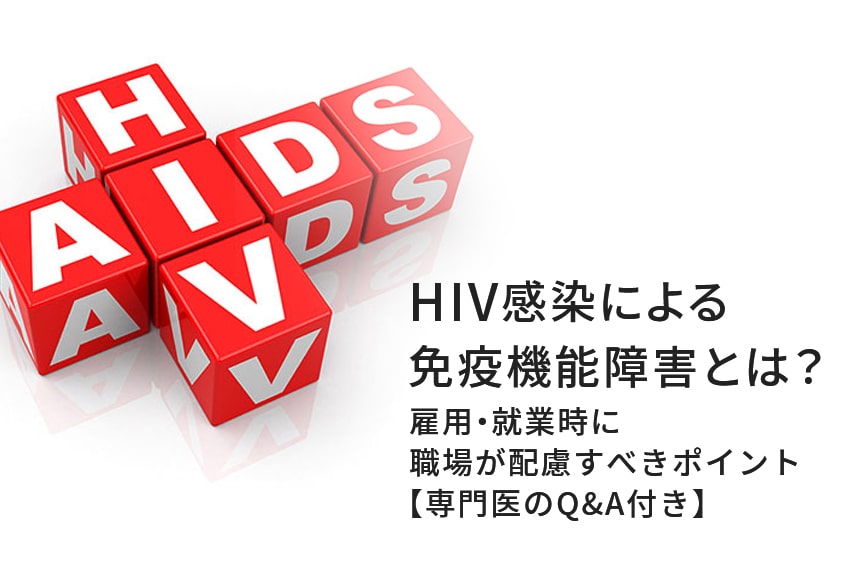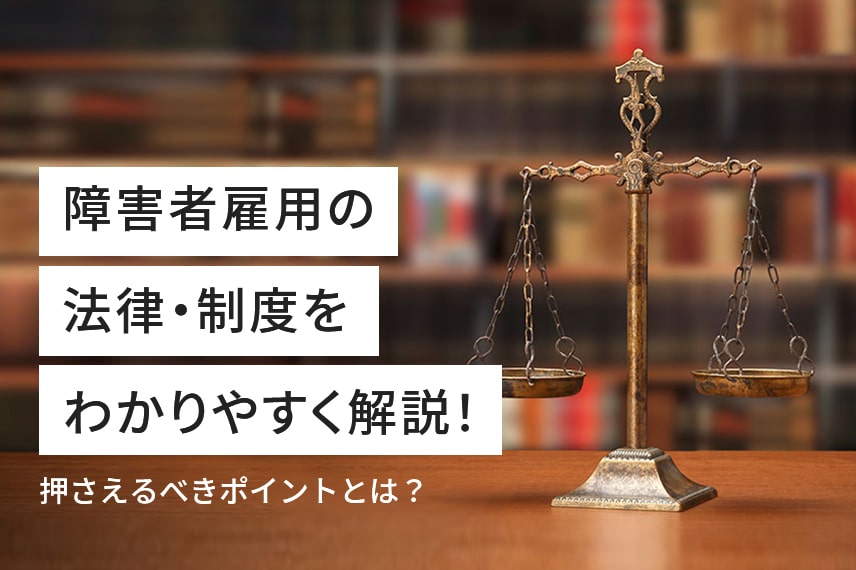作成日:2025年11月17日
障害者雇用を進める企業の中には、欠勤が多い障害者への対応が分からないという担当者も多いのではないでしょうか。休みがちな障害者については、企業が状況を正確に把握し、適切に対応していく必要があります。
本記事では、欠勤が多い障害者への対応に困っている担当者に向けて、欠勤が多い時に考えられる理由と対策について解説します。本記事を参考にしていただき、はたらきやすい職場環境を実現し、障害者雇用における定着率の向上を図りましょう。
- 目次
-
「欠勤」とは?休職や休業との違いなど

障害者雇用における欠勤時の原因や対策について解説する前に、「欠勤」の一般的な意味と、混同されがちな「休業」や「休職」との違いについても理解しておくことが大切です。
そもそも「欠勤」という言葉は、労働基準法には記載されていません。一般的には、従業員の都合によって、本来出勤すべき日に仕事を休むことを意味するとされ、その具体的な内容は企業の就業規則に委ねられています。
休職や休業についても同様に法的な定義は存在しません。一般的に、休職と休業は以下のような意味だと解されています。
<休職と休業の意味>
・休職:従業員について、労務に従事させることができない、または不適当な事由がある場合に、企業がその人に対し労働契約関係を維持しながら、労務への従事を免除または禁止すること
・休業:従業員が労働契約にしたがって労働の用意をなし、しかも労働の意思があるにもかかわらず、その給付の実現が拒否され、または不可能となった場合のこと
障害者雇用において欠勤が多い時に企業が取るべき対応

雇用している障害者の欠勤が多い場合、企業の担当者は状況を迅速かつ正確に把握し、対応することが重要です。障害者が希望を持ってはたらくことができるように、事前に対応について確認しておくことをおすすめします。
ここでは、障害者雇用において欠勤が多い場合の企業が取るべき対応について解説します。
欠勤中の連絡ルールを決める
障害者の欠勤が起きた時点で、欠勤期間中の安否確認のため、連絡手段や連絡先、頻度などのルールを決めておきます。同時に、通院の状況を確認し、必要性がある場合は通院を促すことが必要です。
面談を実施する
当該障害者が、コミュニケーションがとれる状態であれば、早期に面談の時間を設定し、状況の確認や今後の対応についての方針を検討します。面談は、一度だけでなく、定期的に実施することが重要です。
特に欠勤中の場合、面談を実施することに抵抗感を抱く人も多いため、まずは30分程度、電話などで話をすることから始めることが一般的です。
面談は、障害者との今後の方針を決定づける重要な目的があります。円滑に実施するために、面談の流れとポイントを押さえておくことが大切です。
面談の目的を共有する
まず、対象となる障害者に向けて、障害者の状況確認と復帰に向けたステップを検討するという面談の目的を共有することが重要です。
企業としては、適切な対応を講じていくために、障害者の状況についてヒアリングする必要があります。状況を正確に把握するために、話しやすい雰囲気を作ることが大切です。
対象となる障害者からヒアリングする
面談の目的を共有したら、対象となる障害者からヒアリングを行います。事前にヒアリングする内容を押さえておくと円滑に面談を進められるでしょう。
主に、以下の内容をヒアリングします。
<欠勤中の障害者に対する主なヒアリングの内容>
・体調
・主治医の見解
・業務や就業環境
・職場の人間関係などの状況確認
・困り事に関する全般の相談事
・復帰に関する希望や配慮
特に、主治医の見解は、復帰時期や配慮など今後の方針を決めるための基本となる重要な情報です。
必要に応じて、診断書の提出を依頼します。
今後の方針を検討する
必要なポイントをヒアリングしたら、対象となる障害者の希望と、主治医や産業医、支援機関担当者などの専門機関の意見も交えながら、企業として取るべき方針を決めていきます。
この時、欠勤中の障害者の状況や希望、主治医の見解、合理的配慮の指針を参考にして、可能な限り障害者に寄り添いながら、企業として対応できることと、できないことを整理していくことが大切です。
また、面談が一度きりとならないように、次回の面談を設定します。
障害者雇用において欠勤が多い場合に考えられる理由と企業が取るべき対策

欠勤が多い障害者に対して企業が適切に対策を講じていくためには、欠勤が多い理由を把握することが重要です。決して、無理に出勤させたり、感情的な態度を取ってはいけません。
欠勤が続く時に考えられる理由と企業が取るべき対策に関する解説に入る前に、パーソルダイバースが独自に実施したアンケート調査結果「障害者のはたらく幸せに関する調査」※を基に、障害者雇用の実情について理解しておきましょう。
調査によると、73.2%の人が、はたらくことに関して幸せを感じると回答しており、どのような時に幸せを感じるかという質問に対して、58.2%の人が「新たな学びや自己成長を感じる時」と回答しています。
一方で、はたらく中で幸せを感じられない時について、「休息が取れず、体力的・精神的に不安定になった時」が52.9%、「周囲の関心や、評価・評判が得られない時」が43.5%という結果でした。
この結果を踏まえ、新たな学びや成長、自分の役割を実感でき能動的に社会に貢献できる環境であること、かつ、周囲からの関心や配慮が得られないといった要因が少ない環境であることが、はたらく上での幸せにつながっていることが分かります。障害者を受け入れる企業としては、個々人のはたらき方が異なることを理解し、障害者に対して適正な評価をして関心を持ち、安定してはたらける環境を構築する必要があるといえます。
※調査手法:自社会員を用いた、インターネットによるアンケート調査
※調査対象者:dodaチャレンジに登録する、全国の障害のある就業者 471人
会社内の人間関係に強いストレスを感じている
欠勤が多い理由の一つに、職場の人間関係に強いストレスを抱えていることが考えられます。障害者は、人の言動や表情に敏感であることが多いと言われています。人間関係によるストレスを軽減するためには、コミュニケーションのハードルを下げる取り組みが有効です。
また、前述したパーソルダイバースの調査結果では、はたらく幸せを感じられない時について、「周囲の関心や評価・評判が得られない時」が43.5%、「障害や特性に対する周囲の理解が得られない時」という回答が39.5%という結果が出ています。
欠勤が多い場合、障害者が職場において適正な評価や適切な配慮を受けられていない可能性も否定できません。
ストレスを抱える障害者の多くは、直接自分が厳しく指導されているわけではなくても、周囲の人が厳しく注意されている様子を目の当たりにすることで、自分も同じように叱られるのではないかと恐怖を感じてしまうことがあります。
こうした不安を軽減するためには、現場の状況を正しく把握し、企業や部門ごとに理解を深める取り組みが重要です。
仕事内容や業務量、難易度が合っていない
仕事内容や業務量、難易度が合っていない可能性も考えられます。
調査結果にある通り、「新たな学びや自己成長を感じられる時」にはたらく幸せを感じると回答している人は58.2%となっています。
この結果からも、欠勤が多い場合には、担当する職務が合っておらず、学びや成長につながっているという実感を得られていない可能性も考えられます。
特に障害者雇用の場合、職種が限られているケースもあり、本人のスキルや希望と異なる仕事をアサインしている可能性もあります。企業は、障害者の適性を踏まえ、仕事内容の見直しと適切な配置が必要です。
生活が不安定なケースもある
家族の問題や、経済的な不安など、仕事以外の生活面で問題を抱えているケースもあります。生活面に関する相談への助言については、企業での対応範囲を越えているため、専門家に対応を連携していくことになります。障害者が困らないように、産業医や主治医、障害者職業・生活支援センター、社会福祉協議会などの相談先と連携を進めましょう。
また、企業の担当者は、事前に連携する関係部署や機関の役割分担を明確化させておくことも重要です。必要に応じて、就労移行支援機関やジョブコーチ、外部の障害者の定着支援を手掛ける会社などの第三者機関と連携を取り対応します。
<主な関係部署や機関の役割分担>
・人事:職場の人間関係
・現場の上長:職務
・就労移行支援機関やジョブコーチ:家庭・プライベートに起因する問題
・産業医・通院先の医師:病状の変化などへの対応
欠勤が多い障害者を解雇することはできる?

欠勤が多い障害者に対して、企業は解雇できる場合もあります。ここでは、障害者雇用における解雇について、解説します。
障害の有無にかかわらず解雇できる場合がある
障害者雇用においては、障害の有無に関係なく解雇できる場合があります。ただし、障害者であることを理由に解雇することはできません。
一般的に、企業は従業員の同意なしに解雇を通知できるものと考えられがちですが、実際にはそうではありません。労働契約法では労働者保護の観点から、解雇が認められるのは「客観的にみて合理的な理由があり、社会通念上相当」と判断される場合に限られています。したがって、企業が一方的に解雇を行うことは、法律上厳しく制限されており、正当な理由がなければ無効とされる可能性があります。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
障害者を解雇する際は企業の合理的配慮義務を果たしたかが重要
障害者を解雇する際の判断にあたっては、通常の解雇に関する条件に加え、企業の合理的配慮義務が果たされたかどうかも重要なポイントとなります。
「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、障害者雇用を進める企業には、雇用している障害者の能力を正当に評価して適当な雇用の場を与え、適正な雇用管理や雇用の安定につなげるように努めることが法的に義務付けられています。
「全て事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理並びに職業能力の開発及び向上に関する措置を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。」
よくある質問

障害者雇用を円滑に進めるためには、障害者が適性や希望に合う仕事に就いて、いきがいを持ってはたらくことができる職場づくりが欠かせません。企業が障害者雇用に関する理解を深めていくことが、そうした職場づくりに必要です。
ここでは、障害者雇用に関する「よくある質問」を紹介します。
障害者雇用において有給休暇は付与できる?
有給休暇は、業種や職種、雇用の形態にかかわらず、はたらく全ての人に対して与えられるものであることが、労働基準法で定められています。障害者雇用においても同様に、有給休暇は付与されます。
ちなみに、有給休暇は、6ヶ月間勤務し、かつ、8割以上勤務することで付与されます。原則として、1年ごとに最低10日間の休暇が与えられるというものです。企業によっては有給休暇とは別に、障害者への障害起因による突発的な体調不良に対する休暇制度(無給だが)を整えているケースもあります。
障害者雇用における通院配慮とは?
障害者雇用においては、通院に関する企業の対応が欠かせません。多くの企業では、障害者の通院に関して有給休暇を付与することで対応していますが、平日の勤務時間内に通院できる制度を設けるなど、企業が独自に通院配慮を示しているケースもあります。
通院配慮に関する制度を設ける場合は、就業規則や社内通知などに記載して従業員に共有することが一般的です。
雇用障害者の欠勤が多い場合の法定雇用率制度におけるカウント方法は
欠勤、遅刻などにより、実労働時間が所定労働時間を下回る月が年間の半分以上(7ヶ月以上)ある場合は、実労働時間が基準となります。例えば、週所定労働時間が30時間以上の常用労働者の場合、月120時間に満たない月が年間の半分以上あると、「常用労働者数」も「雇用障害者数」も0.5カウントとなります。
そもそも法定雇用率制度とは、従業員が一定数以上規模の企業において、障害のある従業員の割合を「法定雇用率」以上に雇用することが義務付けられている制度のことです。法定雇用率が未達成の企業で常用労働者が100人超の企業については、障害者雇用納付金が徴収されます。
法定雇用率制度における障害者数のカウント方法は、障害の種類や程度によって異なる点が特徴です。
| 週所定労働時間 | 30H以上 | 20H以上30H未満 | 10H以上20H未満 | |
| 身体障害者 | 1 | 0.5 | ー | |
| 重度 | 2 | 1 | 0.5 | |
| 知的障害者 | 1 | 0.5 | ー | |
| 重度 | 2 | 1 | 0.5 | |
| 精神障害者 | 1 | 1(※) | 0.5 | |
※当分の間の措置として、精神障害者である短時間労働者は、雇入れの日からの期間等にかかわらず、1人をもって1人とみなすこととしている。
まとめ

本記事では、障害者雇用において、欠勤が多い場合に考えられる理由と対策について解説してきました。
企業が欠勤の理由や状況を正確に把握し、迅速かつ適切に対策を講じることで、障害者の定着率向上が期待されます。障害者の状況把握のために、コミュニケーションがとれる状況であれば定期的に面談を設定し、目的を共有した上で丁寧にヒアリングする必要があります。ただし、仕事以外の内容に関しては、関連する専門機関と連携を取り、対応を任せていくことになります。
障害者雇用は、一定の企業において法的に義務化されています。障害者が安心感を持ってはたらくことができる職場環境を実現するために、本記事を参考にして円滑に障害者雇用を進めていきましょう。
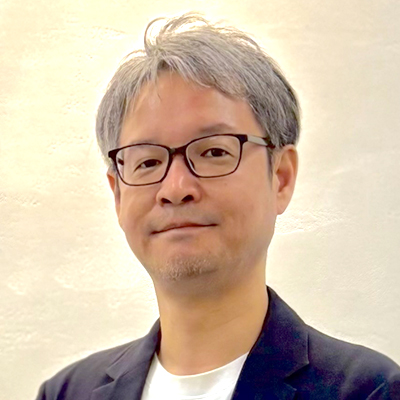
パーソルダイバース株式会社
法人マーケティンググループマネジャー
安原 徹
◆経歴
新卒でベンチャー系コールセンター会社に入社し、営業およびスーパーバイザー業務に従事。その後、株式会社エス・エム・エスにて看護師の人材紹介業務および医療・社会福祉法人の営業を担当。2016年にパーソルダイバース株式会社に入社し、キャリアアドバイザーおよびリクルーティングアドバイザー(RA)として勤務。関西エリアにおける精神障害のある方のご支援先の開拓に注力。2021年に関西RAマネジャーに着任。2023年より中部・西日本RAマネジャーを経て、現在は法人マーケティンググループのマネジャーとして勤務。