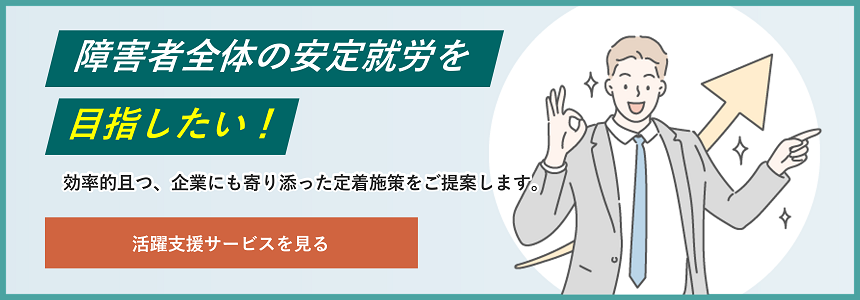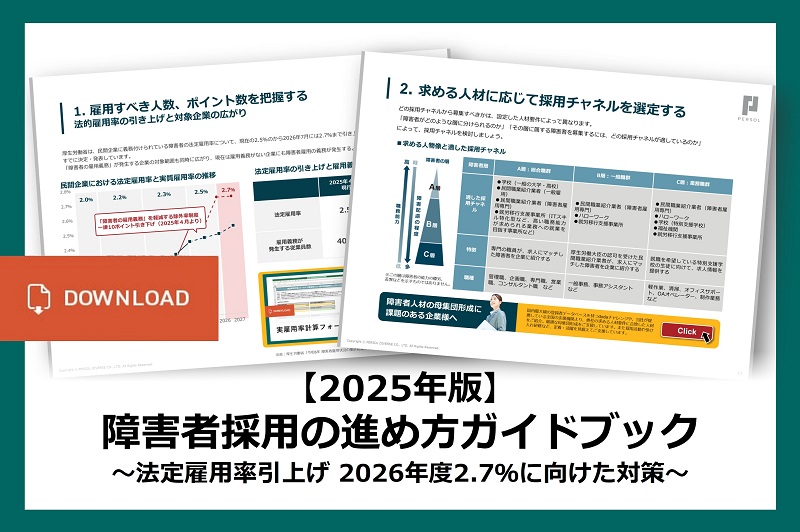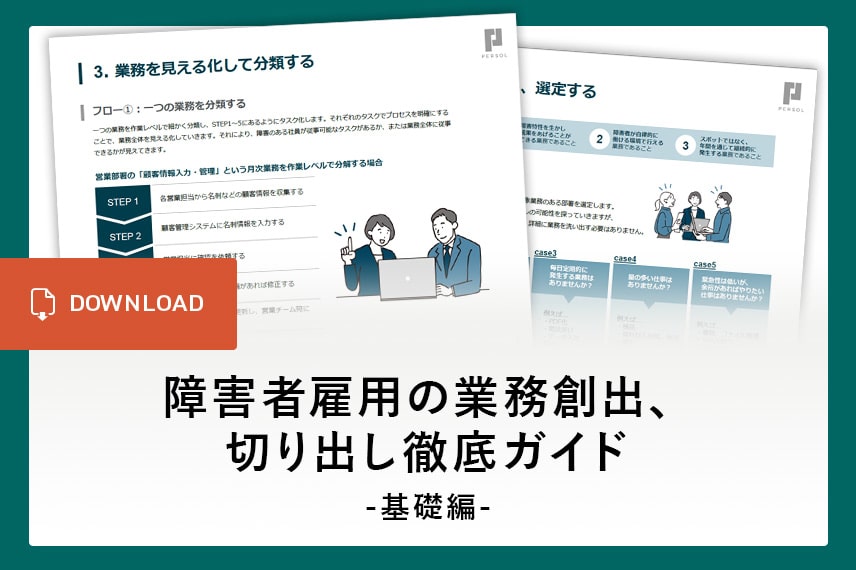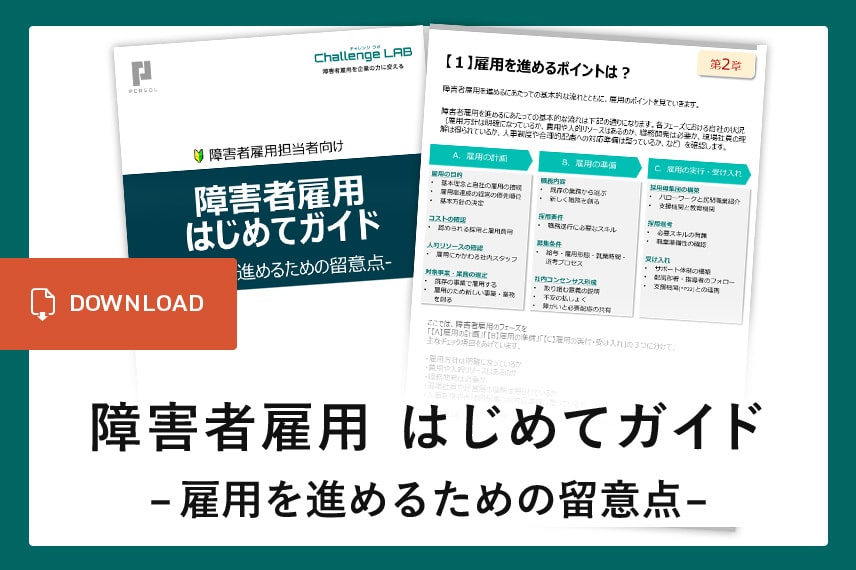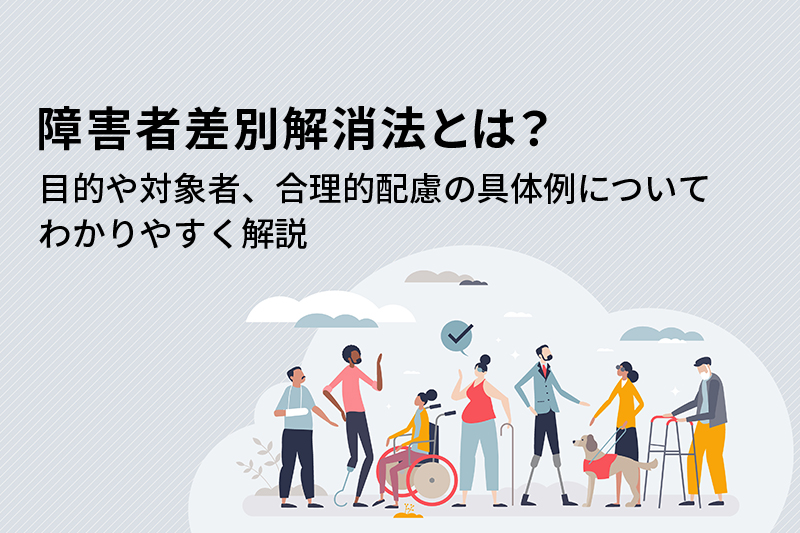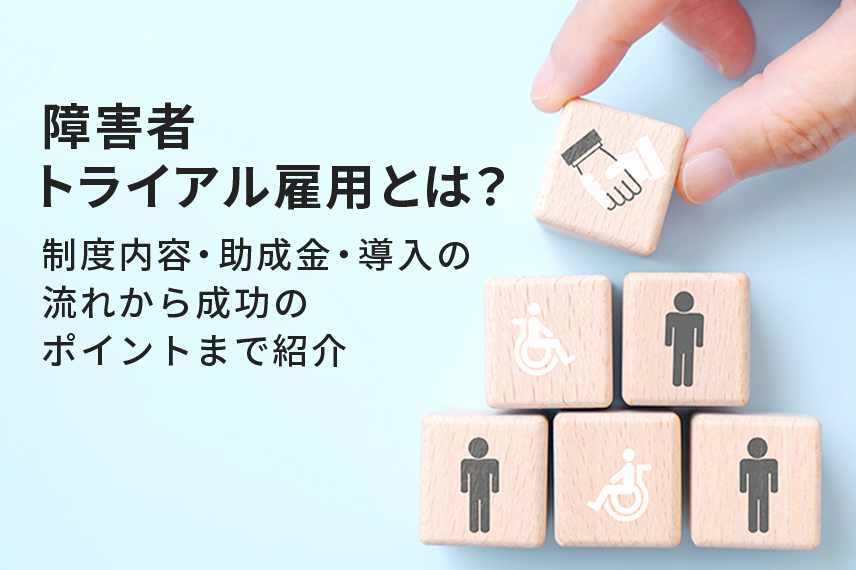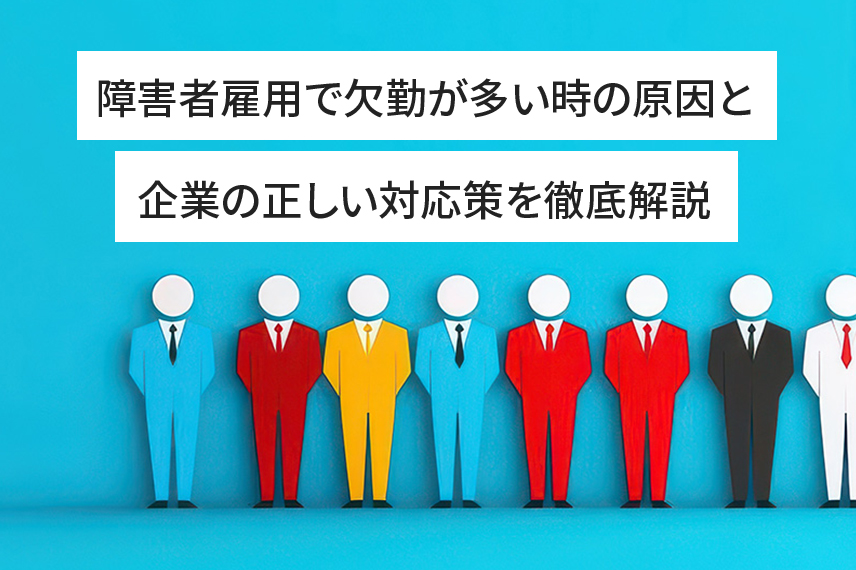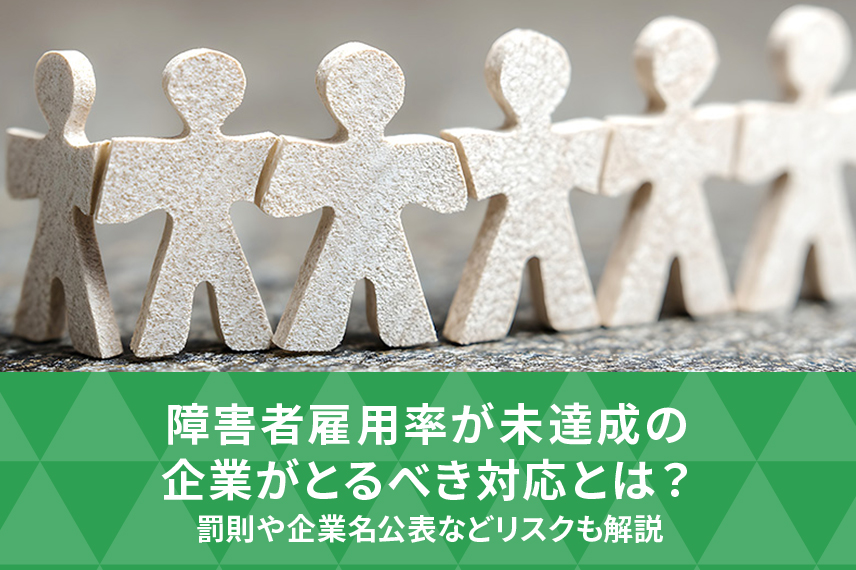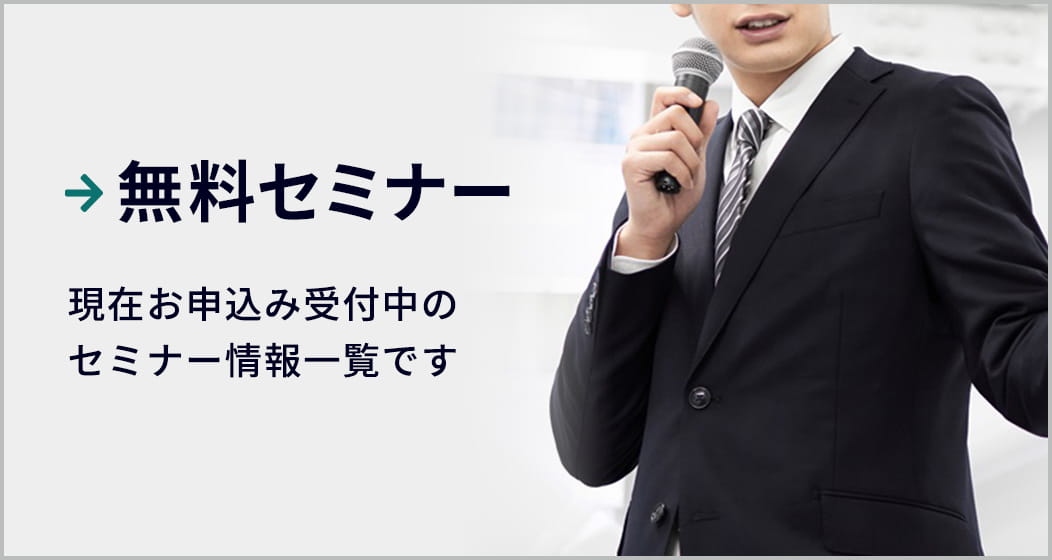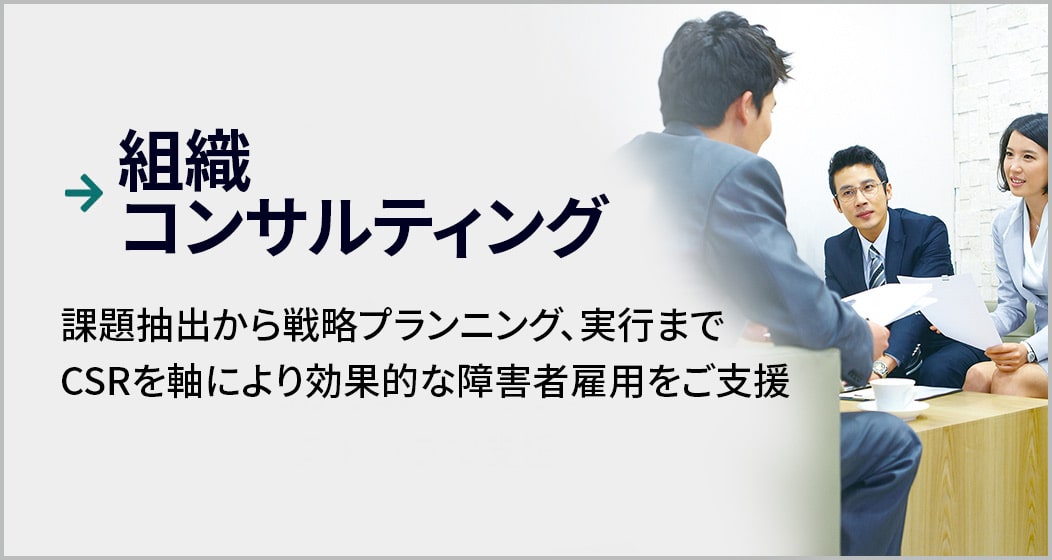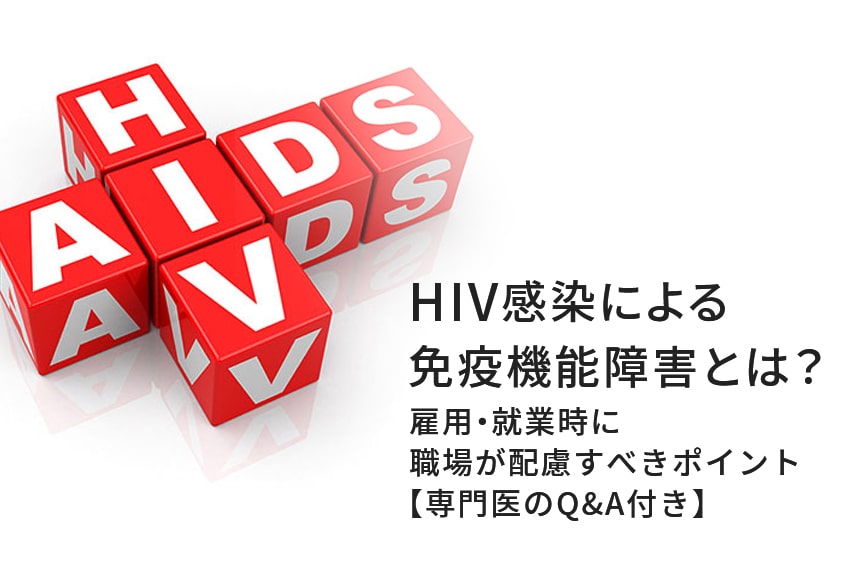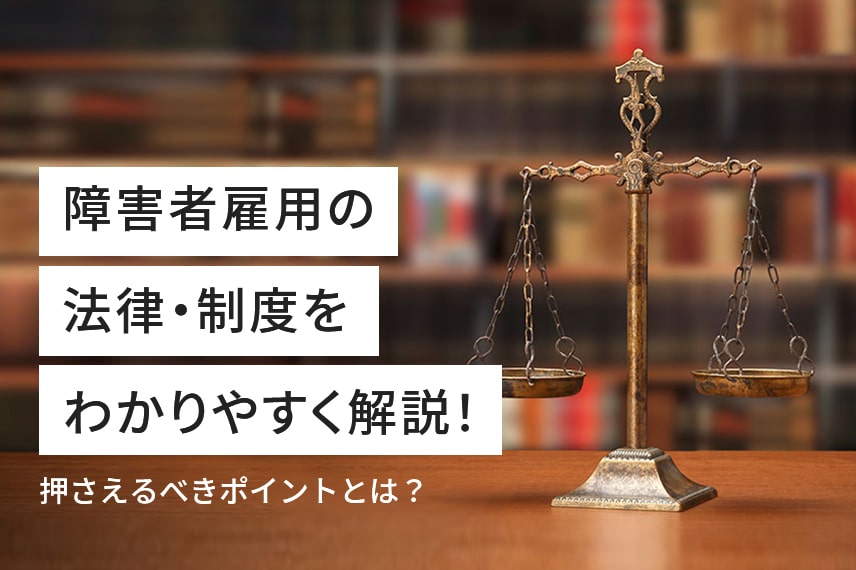作成日:2025年11月4日
障害者雇用を進める企業の中には、ジョブコーチの活用を検討しているものの、種類ごとの特徴や具体的な支援内容、依頼の仕方が分からないというケースもあるのではないでしょうか。
ジョブコーチは、障害者の安定的な就労を目的として、企業や障害者本人などへの支援を実施しています。しかし、ジョブコーチといってもいくつか種類があり、企業の課題に即した形で適切に依頼しなければ、効果的ではありません。
本記事では、ジョブコーチの活用を検討する企業に向けて、種類ごとの特徴や具体的な支援内容、効果的な活用方法などを詳しく解説します。
- 目次
-
ジョブコーチとは?概要をチェック

障害者を雇用する際や、雇用後の定着を図るために、多くの企業でジョブコーチ(職場適応援助者)が活用されています。
ジョブコーチとは、障害者の就職支援の他、企業が雇用する障害者の職場定着を目的として、障害者が職場で円滑にはたらくためのサポートをする人のことです。障害者職業カウンセラーが策定した支援計画に基づいて、障害者や家族、企業などに対して助言をしたり、支援を行ったりします。支援には、障害者手帳の有無は必要なく、双方の合意のみで成立することが特徴です。なお、ジョブコーチの資格は試験を介して取得する国家資格等ではありません。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)や厚生労働大臣の指定する特定の機関が実施する研修を受講し、全てのカリキュラムを履修した人に対して、修了証書を交付することで資格取得となります。
ジョブコーチの活用にかかる費用は、助成金でまかなわれるため、基本的に無料です。
ジョブコーチの標準的な支援期間は、2~4ヶ月ですが、1~8ヶ月の間で個別に設定されるケースもあります。ただし、訪問型ジョブコーチが支援に入る場合は、最長1年8ヶ月まで(精神障害者は2年8ヶ月まで)です。
ジョブコーチの支援対象と役割

障害者雇用を進める企業が、ジョブコーチによる適切な支援を受けるためには、支援対象や役割について理解しておく必要があります。
ジョブコーチの主な支援対象は、職場環境や業務内容などに関する悩みを抱えている障害者です。
そして、ジョブコーチは、事業者や上司・同僚、障害者、家族に対して以下のような役割を担っています。いずれの支援内容も、対象障害者が職務を遂行できるように支援計画に基づいて実施されます。
<ジョブコーチが担う主な役割>
| 対象者 | 内容 |
|---|---|
| 事業主 |
|
| 上司・同僚 |
|
| 障害者 |
|
| 家族 |
|
ジョブコーチ支援は、主に以下の流れで進められます。
<ジョブコーチ支援の流れ>
- 支援計画策定
- 集中支援
- 移行支援
- フォローアップ
まず、障害者本人や職場、職務内容の状況を基に支援計画を策定します。次に、ジョブコーチが主体となり、企業が抱える課題に対して集中的に支援を行います。その後、少しずつ支援の主体を職場の担当者に移行させていきます。
ジョブコーチによる支援は永続的なものではありません。支援を通じて事業所による支援体制の整備が促進され、障害者の職場定着を図ることができれば、支援は終了となります。
ジョブコーチには3種類ある

ジョブコーチには、以下の3種類があり、自社に適したジョブコーチを選択する必要があります。
<ジョブコーチの種類>
- 配置型ジョブコーチ
- 訪問型ジョブコーチ
- 企業在籍型ジョブコーチ
ここでは、ジョブコーチの種類ごとの特徴について解説します。
配置型ジョブコーチ
配置型ジョブコーチとは、地域障害者職業センターに配置するジョブコーチのことです。就職することの困難性が高い障害者を重点的な支援対象としています。
配置型ジョブコーチが自ら支援する他、他の訪問型ジョブコーチや企業在籍型ジョブコーチと連携しながら、必要な援助や助言などの支援をしていくことが特徴です。
訪問型ジョブコーチ
訪問型ジョブコーチとは、障害者に対する就労支援を実施する社会福祉法人などに雇用されるジョブコーチのことで、企業に訪問して障害者の就労を支援します。必要な経験と能力を有するジョブコーチによる支援を受けることが可能です。
具体的な支援には、障害特性に配慮した雇用管理や配置、職務内容の策定が挙げられます。その他、上司や同僚に向けて、障害者への指導方法についての助言を行うことも訪問型ジョブコーチの支援内容です。
企業在籍型ジョブコーチ
企業在籍型ジョブコーチとは、障害者を雇用する企業に雇用されるジョブコーチのことです。
支援内容は、訪問型ジョブコーチと基本的に同じですが、企業在籍型ジョブコーチは、障害者がはたらく職場に在籍している点が異なります。そうした特徴から、よりきめ細やかな支援をしやすいという利点があります。
企業在籍型ジョブコーチの重要性
近年、障害者雇用数の増加に伴い、ジョブコーチの支援に対するニーズも増加しています。企業在籍型ジョブコーチの導入支援策として、厚生労働省は障害者雇用安定助成金の制度を作成しました。国としては、職場適応援助者の育成・確保のため、障害者就労を支える人材の民間検定の資格化を検討しています。
今後も障害者就労を支える人材ニーズが高まることが想定されており、人事担当者としてのキャリア形成においても重要度は増すと考えられます。
3種あるジョブコーチの選択について
障害者雇用を進める企業は、配置型や訪問型、企業在籍型といった3種類のジョブコーチにおける役割について理解を深め、自社に適した形で活用していく必要があります。特に、初めてジョブコーチを利用する企業においては、配置型と訪問型ジョブコーチでの利用が一般的です。
他方、企業在籍型ジョブコーチに関しては、障害者を多く雇用する特例子会社や大企業に代表されるような、障害者が対応する業務を集約・組織化した部署にて配属する「集合配置型」の雇用を実施している企業に適しています。
多くの企業においてジョブコーチの配置が重要視される中、一時的な活用なのか、あるいは障害者雇用推進にあたっての企業全体の体制拡充が必要なのか、目的に沿った選択が必要です。
企業がジョブコーチを利用する方法
企業がジョブコーチを活用する場合、専門機関・社会福祉法人等へ直接依頼する必要があります。企業内における障害者の受入体制や職場環境の改善提案などの支援、障害者の適性判断、業務との相性などに関する助言を受けられます。
配置型ジョブコーチへ依頼する場合は、地域障害者職業センターへ問い合わせをします。地域障害者職業センターは、各都道府県に1ヵ所以上設置されている機関のことで、無料で利用することができます。
障害者雇用を進める企業は、自社が抱える課題解決に向けて、適切にジョブコーチの活用を検討していきましょう。そして、障害者雇用に対する社内理解を深め、職場環境を整備する必要があります。
自社の社員が企業在籍型ジョブコーチになるには?

障害者の雇用を進める企業が、企業在籍型ジョブコーチを配置するためには、以下の方法があります。
<企業在籍型ジョブコーチの配置方法>
- 既存の社員にジョブコーチの資格を取得させる
- ジョブコーチ資格を有する人材を新たに雇い入れる
ここでは、既存社員にジョブコーチの資格を取得させる方法について解説します。
企業在籍型ジョブコーチになるためには、主に以下の研修を受講することが必要です。
・高齢・障害・求職者雇用支援機構による「企業在籍型職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修」(無料)
「企業在籍型職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修」は、集合研修と実技研修の2部構成となっていることが特徴です。対象事業者には一定の要件があるため、事前に高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページなどで確認することを推奨します。
また、自社の社員に企業在籍型ジョブコーチの資格を取らせて、雇用する障害者に向けて職場適応援助を実施する企業には、「企業在籍型職場適応援助促進助成金」が支給される可能性があります。助成金の概要や支給額については、後述します。
その他、民間の研修機構が実施する有料の研修もあります。コストと研修内容を確認して、自社に適した研修を受講することが大切です。
・NPO法人ジョブコーチ・ネットワーク
・NPO法人大阪障害者雇用支援ネットワーク
・NPO法人なよろ地方職親会
・NPO法人くらしえん・しごとえん
・社会福祉法人南高愛隣会
よくある質問

ここからはジョブコーチに関するよくある質問を3つ厳選しました。円滑にジョブコーチ支援を受けるためのヒントとして下さい。
ジョブコーチと就労定着支援の違いは?
ジョブコーチと似た言葉として、就労定着支援があります。就労定着支援は、障害者総合支援法に基づく制度で、2018年4月に創設されました。主に、障害者の環境の変化や生活面の問題を中心として、就労上の問題解決を支えるサービスのことです。
具体的には、各事業所の担当者が月1回以上のペースで雇用されている障害者と面談し、職場環境や生活リズムについてのヒアリングを実施します。そこで課題を把握した上で、本人や勤務先との連絡調整、助言を行っています。
ジョブコーチ支援を受けるまでにかかる期間は?
ジョブコーチ支援を受けるためには、最短でも2週間程度必要です。
ジョブコーチが支援を開始するまでには、障害者と事業主双方の同意が成立する必要があります。また、的確な支援を実施するためには、障害者の特性を把握すると共に、事業所の指導体制や職務内容、職場環境などの分析が欠かせません。
依頼してからすぐに支援を受けられるわけではないことを考慮して、ジョブコーチの依頼に向けて計画的に手続きを進めることが重要です。
障害者を雇用する企業が受けられる助成金は?
企業に雇用されたジョブコーチが自社内で支援を行う場合、企業在籍型ジョブコーチ制度により助成金の対象となる可能性があります。
地域センターが作成または承認する支援計画で、必要と認められた支援を企業在籍型ジョブコーチに行わせた場合に、支給されます。支給額は、企業規模や労働条件などによって異なりますが、1人1万5千円~12万円(月額)です。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に申請することで、助成金の支給を受けられます。
まとめ

本記事では、ジョブコーチの活用を検討している企業に向けて、ジョブコーチの支援対象や役割、種類ごとの特徴などについて解説しました。
ジョブコーチとは、障害者の安定的な就労を目的として、障害者や家族、企業に対して支援を実施する役割のことです。ジョブコーチによる支援は永続的なものでなく、課題が解決され、障害者を雇用する職場環境の整備と障害者の職場安定という目的が達成されると、終了します。
ジョブコーチには3種類あり、それぞれ所属と役割が異なります。ジョブコーチを活用する場合は、種類ごとの支援の目的や役割に対する理解を深め、自社の課題解決に適したジョブコーチを活用することが重要です。
本記事で解説したジョブコーチ制度の概要を押さえて、積極的に障害者雇用を進めていきましょう。
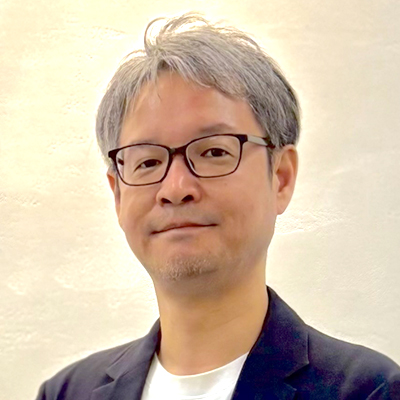
パーソルダイバース株式会社
法人マーケティンググループマネジャー
安原 徹
◆経歴
新卒でベンチャー系コールセンター会社に入社し、営業およびスーパーバイザー業務に従事。その後、株式会社エス・エム・エスにて看護師の人材紹介業務および医療・社会福祉法人の営業を担当。2016年にパーソルダイバース株式会社に入社し、キャリアアドバイザーおよびリクルーティングアドバイザー(RA)として勤務。関西エリアにおける精神障害のある方のご支援先の開拓に注力。2021年に関西RAマネジャーに着任。2023年より中部・西日本RAマネジャーを経て、現在は法人マーケティンググループのマネジャーとして勤務。